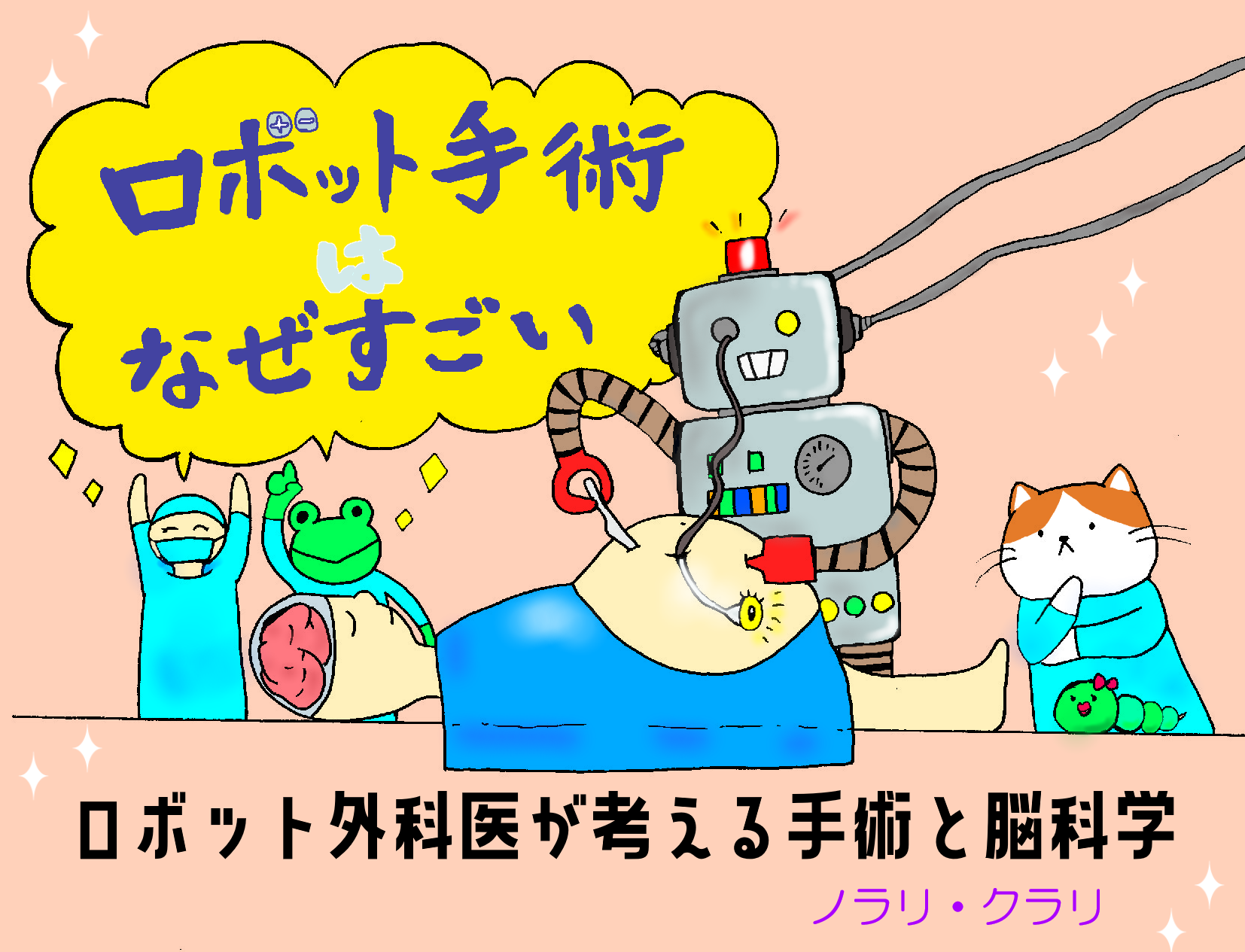お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第40回(最終回)
2025/07/28
第40回 ロボット手術はなぜすごいのか?
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

最後のイラストなので、🖤をいっぱい描きました(ノラリ)。
最後までお読みいただきありがとうございました。
これまで、私は「ロボット支援手術がなぜすごいのか」を、できるだけわかりやすく、脳科学の視点を交えながら、つたないイラストとともに綴ってきたつもりである。少しでもそのすごさに「なるほど!」とか「へぇ!」と感じていただけたなら、とても嬉しい限りだ。一方で、実際にロボット支援手術に慣れた外科医の方々は、「そんな当たり前のことを?」と思われたかもしれない。それは、あまりにもロボット操作に慣れすぎて、そのすごさに気づかなくなっているのだろうと思う。実は名人でさえも、なぜ自分は上手くなったのかということを意識できないのである。この連載を通じて、ロボットの技術的な進化や自分たちの脳の働きのすごさに、改めて気づいていただけたら幸いである。
- 世界は変わり続けている
私たちは日々の生活のなかで、目の前の現実に自分なりの解釈を加えながら、「自分だけの世界」を創りあげ、少しずつ更新し続けている。手術の世界も同じであり、開腹手術、腹腔鏡手術、そしてロボット支援手術と、それぞれの技術によって見える世界や必要なスキルは大きく変わる。ロボット支援手術では、拡張された視覚によって細かい部分まで見えるようになり、高精度な動きができる機能によって、これまでにないレベルの繊細な手術が可能になった。「手術ってこういうもの」と決めつけず、新しい世界を受け入れることの大切さを教えてくれるのが、ロボット支援手術なのである。 - 手術と「記憶」の深いつながり
ロボット支援手術を行う外科医にとっては、手術部位の構造や組織の感触、手順などがすべて、脳に蓄えられた「記憶」によって支えられている。経験を積むことで、必要な場面で必要な情報を瞬時に思い出されて対応できるようになるのである(いわゆる直感である)。特に重要なのは、「質感の記憶」「手術野における微細な空間・位置の記憶」「体で覚えた操作の記憶」である。ロボット支援手術では触った感覚が伝わりにくいため、視覚や深部感覚を通して質感を想像する力がより求められる。 - 意識的な記憶と無意識の記憶
記憶には「意識できる記憶(陳述記憶)」と「無意識のうちに使っている記憶(非陳述記憶)」がある。例えば、手術の前に手順を復習するのは意識的な記憶によるが、実際の手術中に思い出す組織の質感や手の動きは、その場にならないと思い出せない、無意識の記憶である。この無意識の記憶は、一度思い出すと次から次へと芋づる式に関連する記憶が引き出され、手が自然に動くようになる。手術の上手さは、この無意識の記憶の質と量に大きく関わっているように思えるのだ。 - 大脳皮質は「感覚の変換装置」
ロボット支援手術では、「目で見た情報」を「触った感覚」や「空間の認識」に置き換える力が必要である。人は幼い頃から五感を使ってモノの質感を学び、脳に記憶している。例えば、見た目や形だけでなく、触った感触や抵抗など、いろいろな情報を統合して「そのモノらしさ」を理解している。脳にはこのような情報をまとめる「連合野」があり、異なる感覚を組み合わせて判断している。ロボット支援手術では、この変換能力を最大限に活かせるよう、映像の質や操作性に工夫がされている。 - 大脳皮質は「予測の器官」
脳科学では、脳は「未来を予測する装置」として進化してきたとする説がある。手術の熟練者は、目の前の映像だけでなく、その次に何が起こるかを予測しながら動いている。例えば、「今の状況からこの操作でこうなりそうだ」と直感的に感じて、先回りして手を動かすのである。ロボット支援手術では予測する映像に少しだけタイムラグがあるため、脳がそのズレを補正しながら、未来を予測して動いている。この「先読み能力」
- 視覚から触覚を生み出す「感覚の変換」
- 次に何が起こるかを読む「予測の力」
- 質感・空間・動作を思い出させる「記憶の活用」
- 錯覚やクセさえもうまく利用する「技術の可塑性」
- 外科医ごとの個性あるスタイルを「収束化して向上」
こうした脳の能力をサポートし拡張させるのがロボット手術であり、人間の知覚やスキルの可能性を広げる、革新的な医療技術なのである。
最後に──「習うより慣れよ」
手術のように体で覚える記憶(手続き記憶)は、人間がもつ素晴らしい能力の1つである。私も50歳をすぎてからダ・ヴィンチ手術(da Vinci Surgical System)を始め、今では(錯覚かもしれないが)自分の体の一部のように操作できるようになったと感じている。……ただ、スマホの操作手順がわからなくて、同じことを何度も息子に聞くことになり、「オヤジは本当に、ダ・ヴィンチってやつで手術ができているのか」と、とても心配してくれている(笑)。
ロボット支援手術は、「陳述的に暗記して覚える」というより、「非陳述的に慣れて体に覚え込ませる」ことで上達できるように作られている。「習うより慣れよ」で習熟できるように開発されたダ・ヴィンチは、やはり素晴らしい。今後、さらにさまざまな機能の付加や、全くコンセプトの異なる技術革新もあるであろう。そして人間の能力にも、まだまだ無限の可能性がある。
最後になるが、ヒトの脳とAIの相違を、私が学んだ脳科学で解釈すると、ヒトの脳は専門分野では直感(ある程度限られた非陳述記憶群にアクセスする)を利用して対処するが、AIは莫大な意味記憶の中から高速計算・高速解析によって、最適解を見つけて対応する。そしてヒトの記憶、特に無意識の記憶(質感、触感、運動記憶、深部感覚)は過去の経験(試行錯誤)や身体性に基づいている。したがって、ヒトの高度な直感は身体性を伴う技能において優位であり、身体性を持たないAIが優位に立つのは情報処理型の非身体的領域においてである。チェスや将棋など、複雑でもルールのあるゲームにおいては、身体性がないので、ヒトには不可能な高速計算によって、短時間で最適な一手を選び出せる。AIの“直感(厳密には直感ではないが)”は、経験則というよりも統計的推論と高速処理に基づいていて、プロ棋士を上回るようになったのである。一方、外科手術やスポーツ、工芸など微細な身体性を要する領域においては、AIが完全に代替するのは現時点では困難ではなかろうか。
この連載をあらためて、一般の方も含めて、身体的技能の上達論として再読していただければ幸いである。
(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?