お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第18回
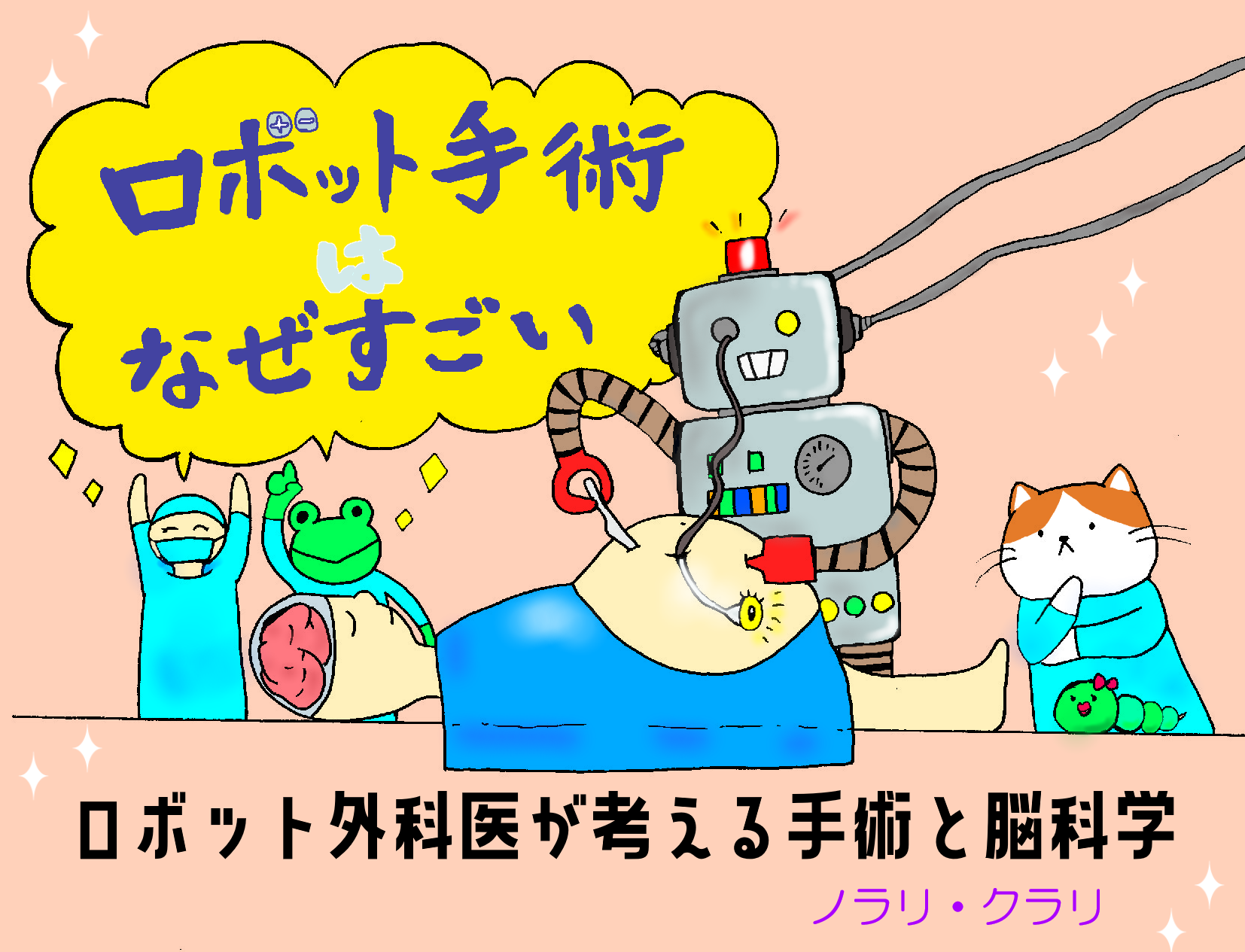
2025/02/24
第18回 何かを考えるということはどういうことか?
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)
考え込むのはどんな時?
昔は手術中にみんなで考え込むことが多かった。特に指導医や執刀医もあまり経験がないような手術をしなければならないときは、あらかじめ頭に入れておくべき術式のアルゴリズムは誰も持っていなかった。画像診断も当時はあまりにも稚拙で、意気込んで開腹してみると、予想以上に進行していて、手術を続けるべきか、あきらめて閉じるべきか考え込んだ。出血の対応も、今のように優れた止血用のデバイスやシートもないし、出血点を押さえたまま、ジーッと対処方法を考え込んだ。
というわけで、手術中に考えなければいけないということが起こった場合は、手術が予想どおりに進まなかった時だ。自分のシミュレーション通りにいかない、あるいは自分の脳内手術モデルと異なる場合だ。
それでは、「何かを考える」とは、どういうことであろうか? ヒトが思考するとき、脳科学的に脳内ではどのようなことが起こっているのか? 知覚したり、運動したりするようなニューロン群の活動であろうか? 「よく考えろ」とか「うまい方法を考えよう」といったときの「考える」とはどういうことだろう。
辞書には、「あれやこれやと思いをめぐらす。そのことについて、心を知的に使って判断する」とある。思いをめぐらす? 判断する? これらは私が考えていた「考える」とはかなり異なる。不安や喜びとともにいろいろな過去のこと、未来のことに思いをめぐらすことが「考える」であれば、あるいは「川が増水してきたので避難すべき」と判断することが「考える」であれば、「考える」とは意識の流れや自由意思のようなものになってしまい、脳科学的には取り扱いの困難な問題となってしまう。
実は考えるという脳内活動は曖昧?
「よくわかりませんね、そのへんの違いは。ぼんやりする――考えごとをする。私たちは日常的にものを考えます。私たちは決してものを考えるために生きているわけではありませんが、かといって生きるためにものを考えているというわけでもなさそうです。パスカルの説とは相反するようですが、私たちはあるときにはむしろ、自らを生きさせないことを目的としてものを考えているのかもしれません。ぼんやりする――というのは、そういう反作用を無意識的にならしている、ということなのかもしれません。いずれにせよむずかしい問題です」
――村上春樹「どこであれそれが見つかりそうな場所で」(『東京奇譚集』新潮社)1)。
この短編集に出てくる老人のように、考えることと、ボーッとぼんやりすることの境界は曖昧である。「考える」という言葉は日常よく使うが、実際のところ、ぼんやりすることの対極にある意味不明の脳活動であるようだ。
われわれは明日行う手術のシミュレーションを行う。腫瘍はどこにあるか、どの範囲を切除するか、血管の解剖との関係はどうか、手順はいつも通りでよいか。画像診断の結果から腫瘍の位置や大きさを確認・記憶して、それに関連する周囲の解剖の記憶や手順・段取りの記憶が次々に芋づる式につながっていく。
このように、「考える」とは、何か課題がある場合に、関連する記憶が次々に連想によってつながっていくことではないだろうか。つまり、関連する記憶をつなぎ合わせ、次に何が必要な記憶か予測することである。関連した記憶を意識してつなぎ合わせることを、われわれは「考える」と言っているのではないか? 脳科学的には、「考える」とは関連する記憶のニューロン群を意識的に結びつけようとする試行錯誤の過程のことではないか? もっと簡単に言えば、思考とは関連する記憶を想起させ、その記憶の中を動くことである。
われわれは、できる限り考えないで物事を成し遂げるほうが楽であるし、なるべく考えないで作業できるように努力しているように思う。手術も考えないで、直感のみで成し遂げれば、そのほうがうまくいくことが多い。何度も同じ手術を繰り返せば、今までの意味記憶が手続き記憶に変化し、無意識にきれいな手術ができるようになる。量が質を凌駕すると言われる所以である。
さて、ロダンの『考える人』は、一体何を考えているのであろうか? もしかしたらボーッとしてるのかもしれない?
文献
- 1)村上春樹:どこであれそれが見つかりそうな場所で.東京奇譚集,pp95-138,新潮社,2007.
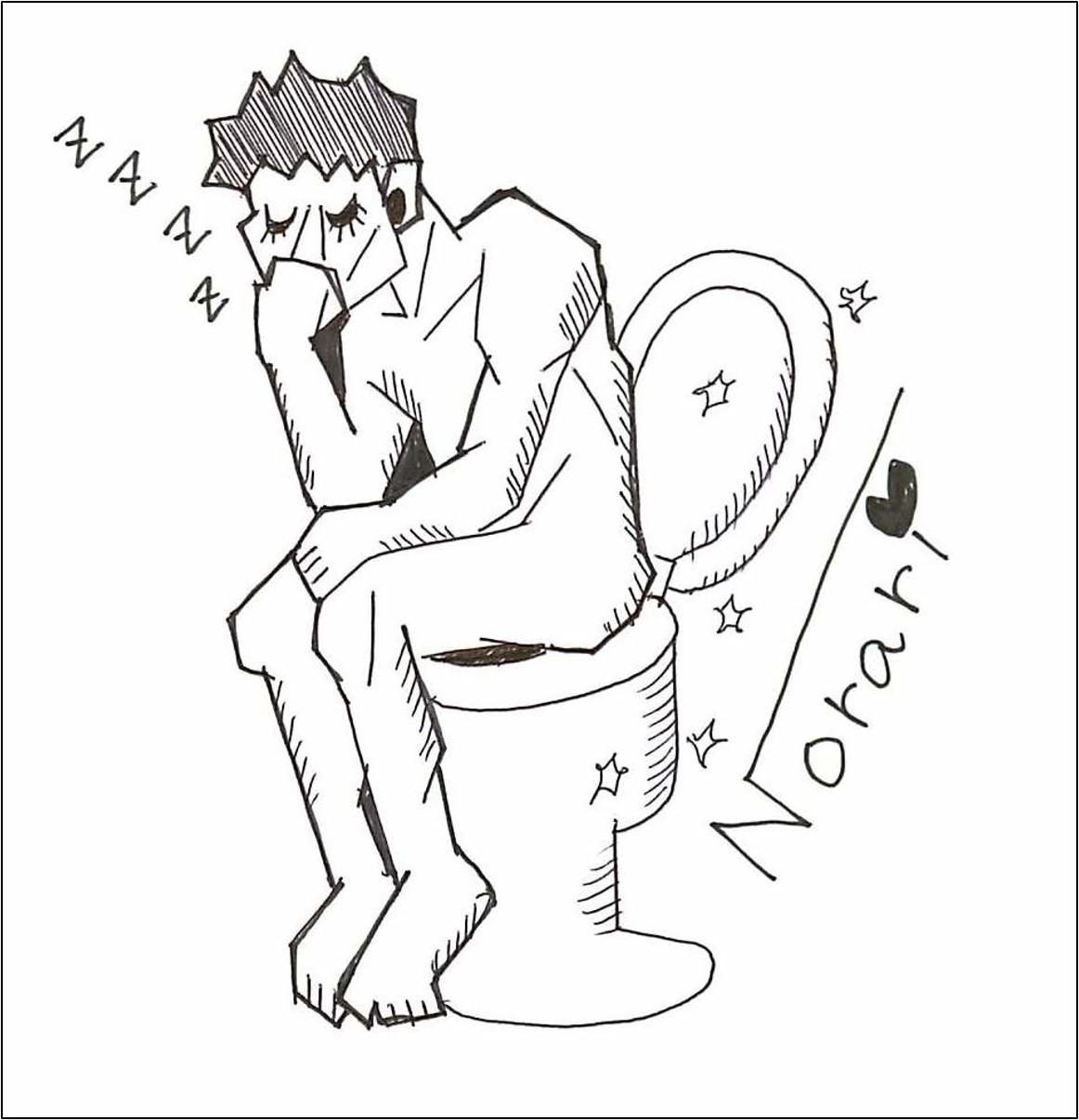
考える人は、何を考えているのか? ボーッとしているのかもしれない?
(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?

