お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第22回
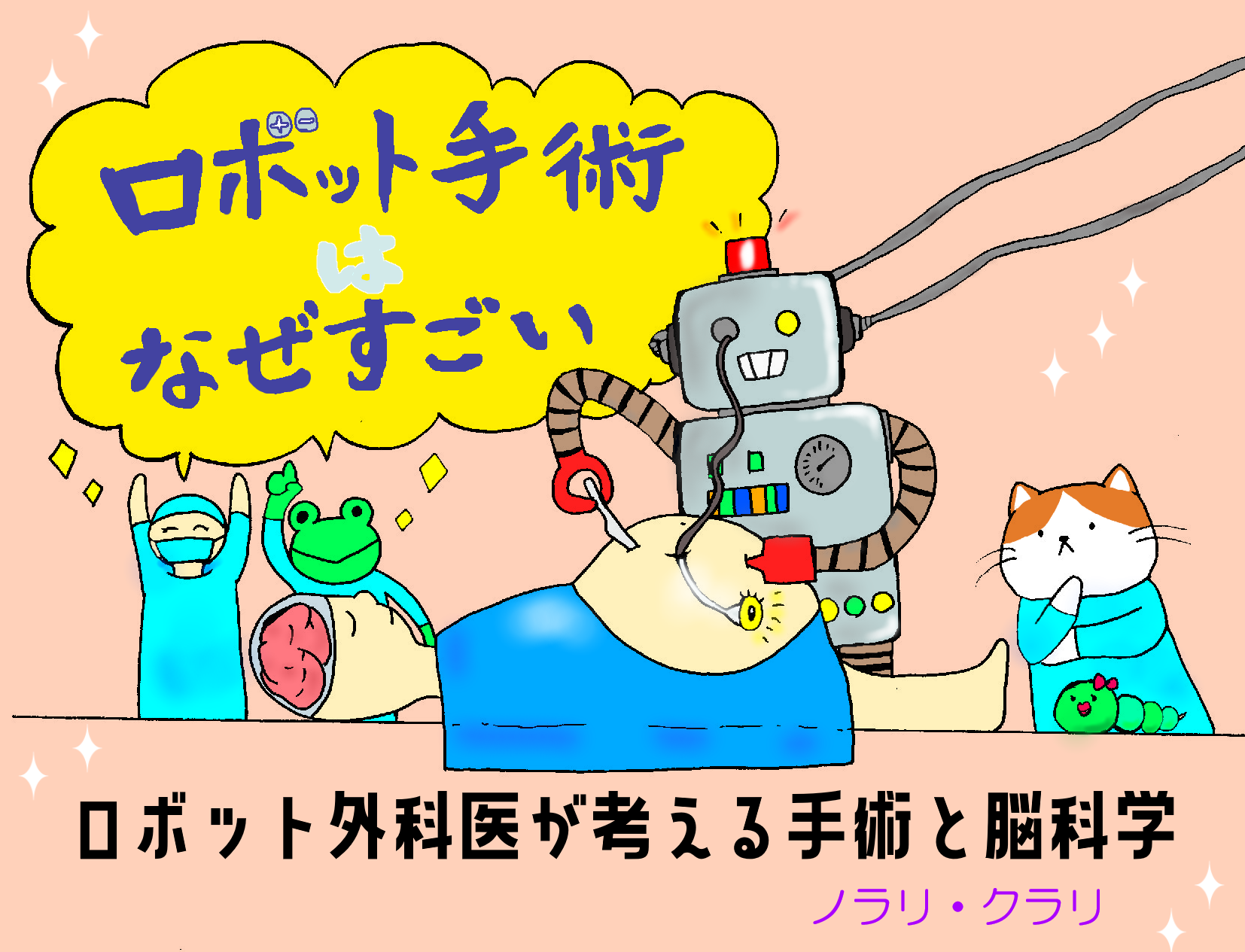
2025/03/24
第22回 ロボット支援手術とは
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)
ロボット支援手術とは?
ロボット支援手術とは、2000年にIntuitive Surgical(インテュイティブサージカル)社製の手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」(da Vinci Surgical System)が、初めて米国食品医薬品局(FDA)の認可を得て、今では世界的に導入されている革新的な手術方法である。本邦でも、2012年4月に前立腺がんに対する前立腺全摘の内視鏡手術用支援機器加算として公的医療保険の適用を受けたことによって、急速に導入が進み、2016年9月の時点で232台のダ・ヴィンチが導入されることになった。2024年1月時点では、700台以上が導入されている。
詳細については知らないが、ロボット支援手術は1980年代後半から、米国陸軍が戦場の負傷者を遠隔操作で治療する目的で開発を進めてきたそうである。この開発競争に勝利したのがIntuitive Surgical社で、ダ・ヴィンチ1台に約3億円がかかる。導入後も1社独占だったので、なかなか安くはならない。
ロボットには、鉄腕アトムのような自律型のロボットと、鉄人28号やガンダムのような人間が操るマスター・スレーブ型(Master-Slave;主人と奴隷の関係)のロボットに分類されるようである。ゆえにダ・ヴィンチは、あまりロボットというイメージはないが、強いて言えば術者に操られて作動するのでマスター・スレーブ型のロボットということになる。患者さんに説明するときは、「ロボット手術でやります」と言うと誤解が生じるので、「ダ・ヴィンチという機器を操作して手術します」と説明したほうが誤解は生じにくい。「ロボット手術」と聞いて、さすがに鉄腕アトムが手術すると思う人はいないだろうと思っていたが、先日、患者さんの奥様が「ロボットが手術してくれる時代になったんですねー」と、いたく感動していた。
ただし、どんどんダ・ヴィンチ手術が増えてくると、マスター・スレーブ型のロボットであるダ・ヴィンチを操るわれわれ泌尿器科医のほうが(本来は主人のはずであるが)、ダ・ヴィンチの奴隷になって働いているように錯覚するのは私だけであろうか? 「ロボット」という言葉は、1920年にチェコスロバキアの小説家カレル・チャペックが書いた戯曲に、初めて登場したらしい。「ロボット」はチェコ語の「強制労働(robota)」に由来し、「人に代わって労働するために、人の姿に模して造られた存在」、それがロボットの原型だったそうだ。あながち私の錯覚は、かけ離れた感覚ではないようである。
人間の直感が操作に連動
ダ・ヴィンチを開発したIntuitive Surgical社の「Intuitive」は「直感的な」という意味である。実際、ダ・ヴィンチを操作してみると、直感的な操作が秀逸で、この社名もまさにピタリとダ・ヴィンチの特性を表現したイカした名前なのである。第2回で直感とひらめきの違いを述べたが、「直感」は本人にも理由がわからない確信を指す。したがって、直感的に操作ができるということは、「こういう具合に手術器具を操作したい」と頭で描いて、手指を動かすと、思い通りに手術器具が操作できてしまうということである。しかも、自分の手指より器用に動く。
大脳基底核の一部は、自転車の運転や泳ぎ方のような一度覚えれば忘れることのない体の運動を制御をしており、実は直感と深く関わっている。ダ・ヴィンチの操作方法は、基本、両手の手指で手術器具を操り、足でペダルを踏みながら見たいところにカメラを移動させ、電気メスで電気を流すのも、別のペダルでスイッチを入れるのである。これら一連の操作は、ゲームのようなシミュレーターを長時間こなして体に染み込ませることによって、直感的に行えるようになる。さらに、実践を積み重ねることによって、実際の人体組織の質感や性質まで、感じられるようになっていく。これも第16回で述べたが、手術には教えられることと教えられないことがあり、後者はいわゆる暗黙知と呼ばれ、実践の場で体得していくものとしか、言いようがない。ダ・ヴィンチも同じだと思う。
しかし、このような素晴らしい手術支援ロボットをIntuitive Surgical社はどのように開発したのであろうか。人間の能力をこれほどまでに拡張するシステムを開発するには、優秀なエンジニアはもちろん、大勢の科学者(特に脳科学者)が結集しているのではないかと邪推してしまうが、詳細は不明である。また当然、外科医の協力や意見のフィードバックが必要で、それこそ数多の試行錯誤を繰り返していると思う。レオナルド・ダ・ヴィンチが「モナリザの微笑」を表現するために執拗に死体解剖を繰り返し、表情筋や口輪筋などの仕組みをあばこうとしたように、鉗子をヒトの手指関節の可動域を超えるように動かすにはどうしたらよいか、何度も試作品を試したことは想像に難くない。
開発の過程は企業秘密であろうが、ダ・ヴィンチの特許の多くは2019年に期限切れとなったため、満を辞して、国内外の新興企業などが参入して手術支援ロボットの開発競争が激化してきた。本邦では国産のhinotori(メディカロイド社)が価格の面で有利なので、ジワジワと追い上げを図ろうとしている。今後、別のタイプの手術支援ロボットも含め、国内外でロボット戦争が勃発してもおかしくはないであろう。

ある患者さんの奥様が「ロボットが手術してくれる時代になったんですねー」と、とても感動していました。
(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?

