お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第3回
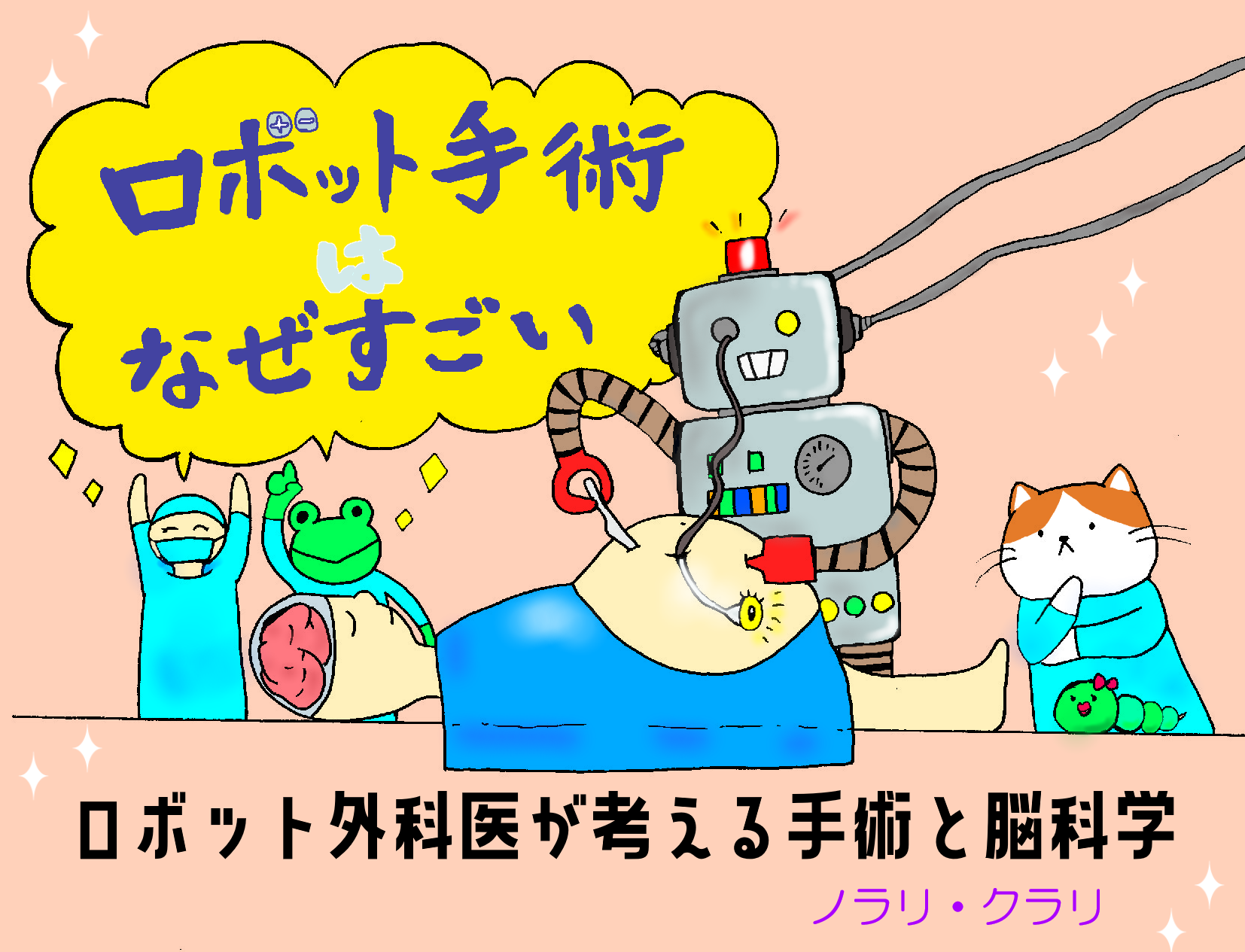
2024/11/12
第3回 ダ・ヴィンチの感覚(質感の記憶):見ることによって触感がわかる?
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)
今年で生誕100年を迎えた安部公房の『砂の女』(新潮社, 1962)を読めば、誰もが砂に触れなくても崩れ落ちてくる砂の感触を実感できる。砂をいじる前から、どんな感覚か簡単に想像できる。すでにわれわれは砂漠のような乾燥しきった砂の感覚や湿った砂の感覚を知っているのだ。
ダ・ヴィンチ(da Vinci Surgical System)手術の短所でもあり長所でもあるが、実はこの手術は触覚なしで行われる。ダ・ヴィンチの手術を始めて一番不思議なことは、人のお腹の中の組織の触感や、組織を把持して引っ張ったときの力加減や、糸を結んで縛るときの強度(強すぎれば糸が切れる)が、視覚情報を基に、あたかも触覚があるかのように感じるようになってくることである。私は「触覚が生えてくる」と皆に言っている。これはわれわれの触覚と視覚の膨大な記憶によるのではないかと推測する。われわれが生きていくうえでは、さまざまな記憶が必要で、記憶によって生きていると言っても過言ではない。いずれこの連載で記憶の分類をまとめようかと思うが、まず短期記憶や長期記憶などの分類があり、長期記憶には陳述記憶(エピソード記憶や知識などの意味記憶)と非陳述記憶(いわゆる手続き記憶で、経験や練習を通して、体で覚えた記憶で一度覚えたら忘れない。よく例に出されるのは、自転車の乗り方やワープロのブラインドタッチなどか)がある。
さて、われわれは生まれたときから、これまで身の回りや、あるいは自然界や都会の建造物のなかで、さまざまなモノの質感や触感を視覚とともに記憶しているではないか。机の上のものから部屋の中のあらゆるものは、見ただけで、どんな触感のものか、簡単に想像がついたり予測できたりする。あるいは外界や自然のあらゆるモノの質感もほとんどは視覚だけで、どんな触感か容易に想像がつくのではないか。赤ちゃんのときから、身の回りのものを見て、触って、舐めて覚えてきたに違いないが、例えばこれらの感覚には、重量感なども記憶しているので、重力の中で進化してきたわれわれには、遺伝子に書き込まれている記憶(いわゆる本能)も含まれているかもしれないが、これら質感の記憶はおそらく体で覚えた非陳述記憶の一種であろう。ただし、誰も指摘していないが、大脳基底核や小脳がプログラムしていると言われる訓練や経験の蓄積を伴う運動技能(手続き記憶)と異なり、容易に、かつ無意識に長期記憶に移行しているのではないか? これらの莫大な記憶は、どんな環境の変化にも順応できるためにあるのではないだろうか。
映画『マトリックス』のコンピュータの作り出した仮想現実の世界にすら、人間は適応していくのである。ダ・ヴィンチ手術の世界は「仮想現実(virtual reality:VR)」というよりは、どちらかと言えば「拡張現実(augmented reality:AR)」である(拡大視野、自分より巧緻性の高い手指の動き、拡張した3Dなど)。われわれがこの手術ロボットを比較的容易に操作できるようになるのは、視覚が触覚を補い、代償していることに相違はないが、われわれ生命が進化上、視覚より先に自分の世界を認識するためにより重要だった触覚を含む皮膚感覚の膨大な記憶が基にあるからであろう。
見て触れる経験が、見る仕組み自体をより触覚に近いものに変化させるのではないだろうか。
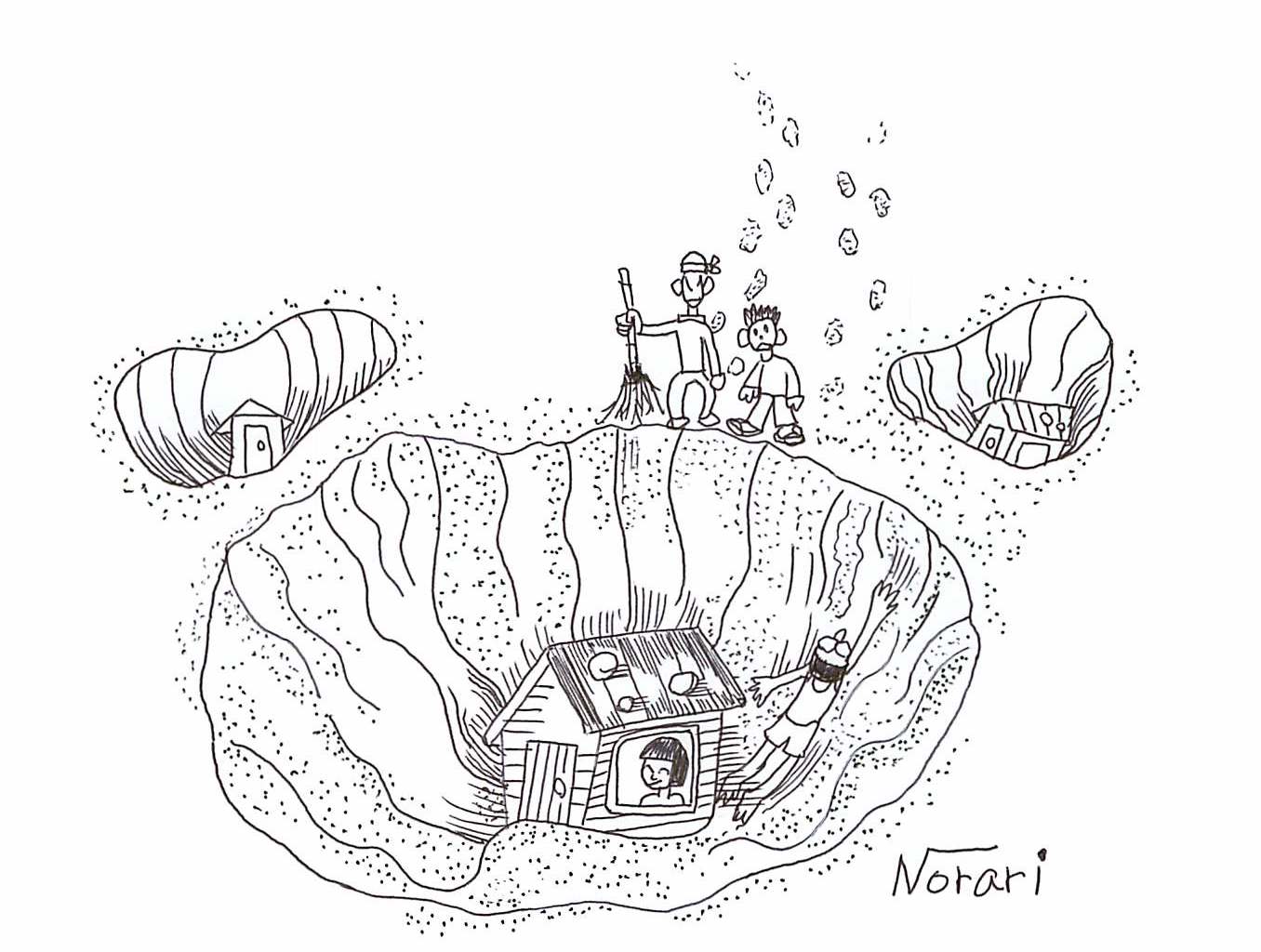
砂の女:砂を見れば、どんな感触の砂かわかる?
(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?

