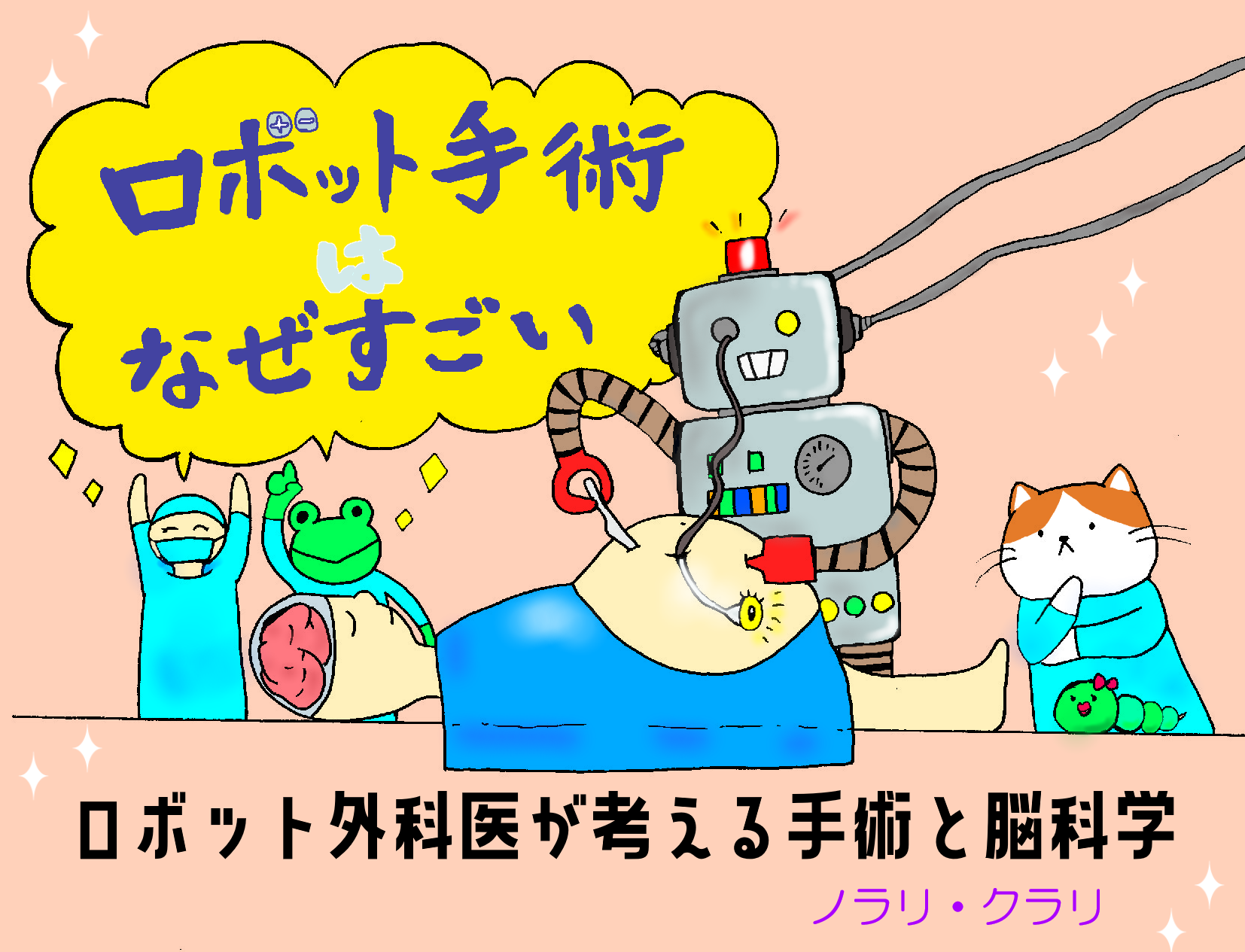お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第34回
2025/06/16
第34回 われわれはエンハンスされている?
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)
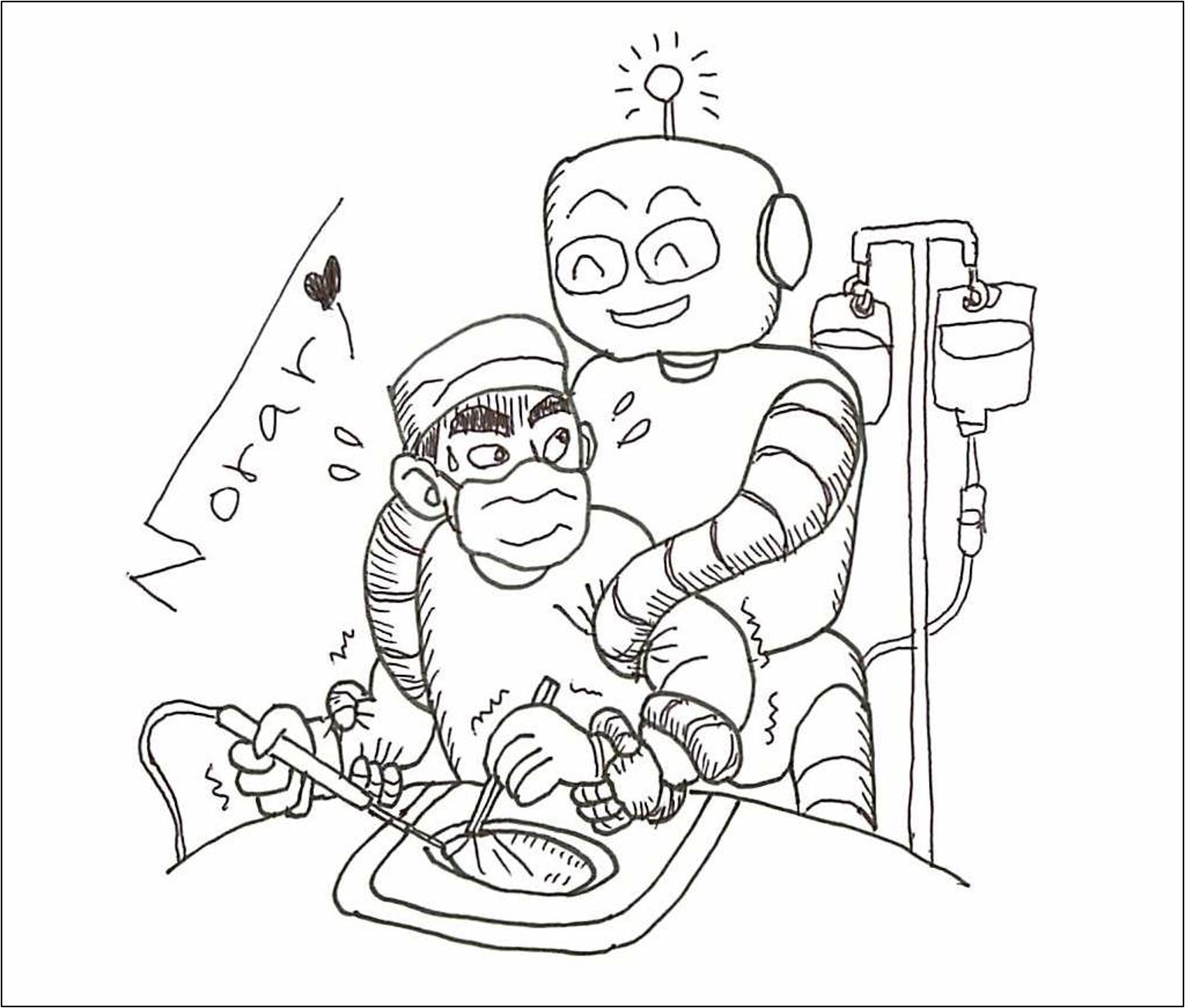
メジャー・サージャン養成ギプス
外科医:手術力をエンハンスしてくれと言ったのに、筋力をエンハンスしても意味がない。これじゃあ、うまくできないじゃないか。
ロボット:うまくできなかったり、失敗した場合は、全てあなたの責任です。
人工知能と天然知能はどこが違うのか?
第25回でも述べたが、AI、いわゆる人工知能がプロのチェスプレーヤーに勝利し、将棋のプロ棋士も勝てなくなって話題になった。これらが可能になったのは、AI に膨大な棋譜を読み込ませ、さらにAI 同士を戦わせ、その対戦過程も読み込ませるという深層学習という手法を取り入れるようになってかららしい。最近は生成AIの台頭により、高度な文章作成や、著名な画家やアーティストの作風で贋作を生み出してしまうほど創造的な仕事をこなせるようになってきたようだ。
医療の世界でも、画像検査や病理検査では大量の画像をAIに読み込ませることによって、人間よりもAIのほうが正確に判定できるようになると言われているし、病気の診断自体も今後AIがさらに、人間的な間違いやバイアスを減らしていけば、いずれ医者の診断能力を凌駕するだろうとも言われている。AIは画像の特徴を詳細に数値化し、その膨大なデータを高速計算・分析したうえで複雑なアルゴリズムに落とし込んで診断するのではと想像したが、実はヒトの大脳のニューラルネットワークを模倣した仕組みのようだ。一方、人工知能の対義語としてのわれわれの“天然知能”は、画像の中から特徴的なパターンを知覚した瞬間に、過去の経験や学習で蓄えたパターン化した記憶群の中から、それと一致するものに瞬時に到達する手法をとる。すなわち、問題の答えをAIはアルゴリズム(計算)によって、そして同じ問題を解くために天然知能は記憶を使うということになる?
それでは、ダ・ヴィンチ(da Vinci Surgical System)による手術は将来、AIに任せても大丈夫であろうか? 手術では、画像や解剖の認識のみでなく、切開・剥離・牽引・切断・止血・縫合などのアウトプットを加えることで刻一刻と術野や状況が変化する。天然知能を有するわれわれは、これらの出力も無意識の記憶のパターンに頼っている。常にアウトプットしながら、次の展開を予想し、先回りしながらパターン行動の記憶を引き出していく。仮に、AIにダ・ヴィンチの名人による手術動画を何千例分か読み込ませたとして、その名人と同等以上の手術ができるようになるかどうかは、AIの専門家でない私にはわからない。もしそのようなAIロボットを私が発明し、完成させ、何とか手術を完遂できるようになったとして、ひとつだけ想像できることがある。
それは、「どんなに手術がうまくできたとしても、達成感や満足感がそこにはない」ということだ。だからこそわれわれは、今のところ、自分の天然知能で何とかやっていこうと考えている。天然知能も悪いもんではない。そしてダ・ヴィンチは天然知能の特性を上手に引き出してくれるような気がしている。実を言うと、ダ・ヴィンチは下手な外科医も上手くしてくれるし、平凡な外科医にも、ダ・ヴィンチによって自分は名手ではないかと錯覚させてくれる。ダ・ヴィンチはわれわれの天然知能をエンハンスしてくれる宝物である。
AI(ChatGPT)にコラムとイラストを頼んだら
いままでの私のコラムを参考にして、ChatGPTに「ロボットが外科医をエンハンスする」というテーマでコラムの作成を依頼すると、1分もかからず、コラムというより、物語が出来上がった。
単純な執刀はロボットにお任せ?—「手術が下手でも上手くなる」時代の話
昔むかし、外科医は「手先の器用さ」がすべてだった。
手術に怖じけるようなら引退すべし。糸結びや縫合が下手なら他の科へ行け。そんな“外科職人主義”がまかり通っていた時代もあった。
ところが今、現場には無言で動くもう一人の“名人”がいる。そう、ロボットである。正確には「ロボット支援手術システム」、たとえばダビンチである。細いアームを自在に動かし、拡大視野で細部まで見分け、ブレない手術をする。
まさに人間離れしたスーパーサージャン。しかも疲れない。手が震えない。怖じけない。文句も言わない。手術が下手でも、ロボットが上手にしてくれる?
冗談のようだが、実はあながち間違ってはいない。
ある若手外科医は、こう言った。
「昔なら“自分には手術の才能がないかも”と思ったかもしれないけど、ロボット手術だと“なんか上手くいって”しまうんですよね…」
それもそのはず。ロボットが勝手に手術するわけではないが、操作する人間のミスやユラギを補正し、動作をなめらかに変換してくれる。
たとえば、ちょっと手の動きがブレても、画面上では“スーッ”と動いて見える。まるで運転のヘタな人が、自動ブレーキ付きの車に乗ってるような感覚である。
ベテラン外科医 vs ロボット
あるベテラン外科医は、ロボット導入に不満を漏らした。
「新人が“先生、僕もロボットでやればいけます!”って言ってくるんですよ。あれ、ズルいよなぁ…」
だがしばらくすると、こう付け加えた。
「…でも、やらせてみると意外と上手いんだよ、これが。なんか…腹立つけど(笑)」どうやら才能は、ロボットのアシストで補えるようだ。
ロボット手術の本質は、「技術を標準化する」ことにある。
「神の手」の手技に頼らずとも、多くの外科医が一定以上の成果を出せる。これは医学の世界にとって革命的だ。もちろん、経験も知識も大切だが、「手先の才能」による“向き不向き”の壁は、確実に薄れている。
「それでも、人間の味は残してほしいなあ」
ただし、ロボットはまだ「空気」は読めない。
患者の不安、術中の微妙な変化、助手との目配せ。
そこにはまだ、人間の“センス”が必要だ。
ロボット手術は、「下手な外科医を一流にする機械」ではなく、一流に近づくための拡張装置(エンハンサー)なのだ。
結論は、ロボットが上手にしてくれる、けど…
ロボットがうまくやってくれるからって、自分が上手くなったと勘違いしてはいけない。それでも、「自分にもできた」と感じられる体験は、未来の名医を育てる一歩になるかもしれない。
手術が上手くいった時、ロボットがそっとささやく。
「いい仕事でしたね、先生。でも8割は私の力ですけどね」と。
どうです? なかなかよくできてますよねー。
今回は、面倒くさくなったので、イラストの作成もAIに頼みました。以下の2つはAIによるイラストです。それを見て、ノラリが冒頭(キャプチャー)のイラストを描きました。イラストはノラリのほうが面白い?


(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?