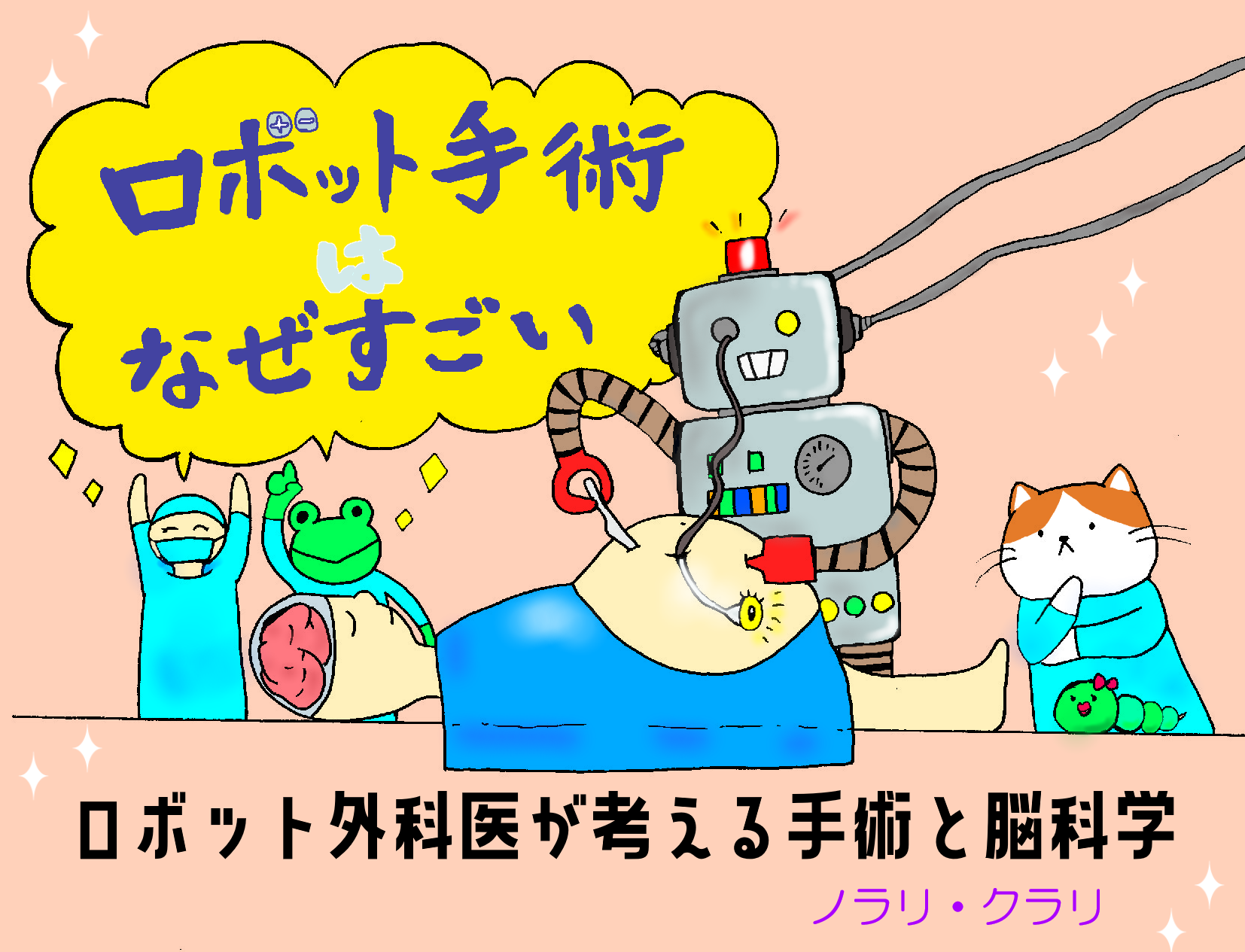お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第37回
2025/07/07
第37回 曖昧な記憶と外科医の不安
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

実は、アイマイやアヤフヤが得意な人もいるかも。
曖昧な記憶と正確な想起
現代の医療では考えられないが、がん患者さんに「がんである」とは告げないで治療をしていた時代があった。ほんの20~30年前の話である。当時は、自分が「がん」だと患者さんになんとなくわからせるというのが医師の話術の一つであった。がんの治療が進歩してくるようになると、がんとは告げないで治療するわけにはいかなくなったので、がんと診断がついたら告知して、治療方針を相談しようということになった。
がんの告知の黎明期に、がん患者さんのご家族から、「本人にがんだと告知すると、われわれも対応に困るから、曖昧にしておいてほしい」と言われ、「どのように曖昧にしたらよいか、困った…」と医局で同僚にこぼしたところ、後輩のシャキシャキした女医さんに、「先生は曖昧が得意じゃないの」と笑われた。普段、自分でも優柔不断を自覚してはいたが、曖昧が得意とはどういうことか? ところが曖昧なのは私だけでなく、患者さんの記憶も曖昧であった。われわれが苦慮してがんの告知をすると、「わかりました。心配するので家族には言わないでください」と言っていた患者さんが、「私はがんではないらしい」とか「どうやらバイキンに侵されたらしい」と同部屋の患者さんに話しているのをしばしば見かけた。当時は患者さんの側にも「医者が本当にがんだと言うはずがない」という思い込みがあって、自分の都合の良いように記憶を改変したのかもしれない。このように、エピソード記憶(陳述記憶)は自分の都合や時間の経過によって書き換えられる可能性があり、実は曖昧である。
これまで記憶の仕組みを述べてきたように、家族や友人の顔を頭の中で思い浮かべようとしても曖昧にしか思い浮かばないが、実際に会えば、即座に彼らだと認識できる。われわれは静止画を見ても、写真で撮ったような完全な記憶はできない。その代わり、ある程度の時間と空間の広がりをもって記憶している。あるいは、周辺の事象と連鎖または混合して記憶されている。そしてとても重要なことは、それらが曖昧だということである。
ボールの軌道のようなモノが重力で落ちる動き、メロディー、単語、漢字、匂い、味といった、意味記憶も手続き記憶も曖昧に記憶されている。しかし、ボールが飛んでくればその軌道を予想できるし、漢字の細かいところがわからず書けなくても、書かれた漢字を読むことはできる。目の前に記憶したものが現れれば、記憶は正確に想起されるのである。
外科医の不安
外科医の年代や経験の多寡によっても違うであろうが、手術の前は多かれ少なかれ、うまくいくかどうか不安を抱くものである。ましてや、初めてチャレンジする難手術や、日本で初めて行われる臓器移植手術など多くの人が注目するような手術であれば、なおさらであろう。ほぼ毎日やっているような手術でさえ心配になることがあるので、画像で腫瘍の位置・大きさを確認するのはもちろんのこと、手術の手順や外科解剖を手術までに何度も手術書や頭の中で確認する(手術のシミュレーション)。超難関手術であれば、それこそ手術が決まった何カ月も前から、不安により脳内シミュレーションが自動的に繰り返される。それはたとえ毎日やっている手術であっても、一連の流れを写真やビデオのように正確に記憶できていないからではないだろうか。あるいはうまく成功した時の体験も、曖昧に記憶されているからではなかろうか。
ところが、いざ手術が始まってみれば、術野の展開や組織の構造を見た瞬間に、「この部位にはこのような組織の特徴があり、このように対処すべき」と直感が働くのは、曖昧な記憶が過去の具象的な展開と一致することが即座に確認されるからであろう。これら非陳述記憶は、想起された際は脳内に正確に記憶されていたように感じるが、実はいくつかの特徴を層状に積み重ねたように、ひとかたまりの構造上の記憶として、曖昧に記憶されているのである。そのため手術前には正確に想起できなくて、外科医は不安に陥るのだ。
どの組織や解剖にも固有の法則がある。組織や解剖を見れば、その法則が曖昧な記憶から想起され、微妙な差異に対応できるようになる。不思議なことに、手術前にあれだけ不安でさまざまなことを想定していても、多くは杞憂であって、実際の場面に直面すると自動的に適切な対応ができることが多い。
直感の世界において、例えば強打者が曲がってくるボールの軌跡を、プロ棋士が中盤の盤面を、あるいはわれわれ外科医が術野の構造を認識するのは、感覚神経からのインプットが脳内で知覚されるということではあるが、知覚とは軌跡や状況や構造を計算したり、分析したりすることではなく、脳内に蓄積された莫大な記憶のなかから、最も近い記憶にアクセスすることではないか。それでも、不安に対する術前の準備(シミュレーション)はよく眠れるようにやっておくべきであろう。

外科医の不安は、今までうまくいった手術でさえも、綺麗に視覚化して想起できないところにあるのではないか? なかにはしっかり言語化して覚えていて、不安にならない外科医もいるらしいが。
曖昧なダーウィン
曖昧さの利点に関して、進化論で有名なダーウィンについて語ろう。彼はビーグル号航海後の20代後半には、おそらく進化論の概要あるいは青写真をつかんでいたようであるが、公表はせず田舎に引きこもり、進化の証拠集めのため、自ら動植物を飼育・栽培し、関連する知識の収集に努めていた。ただし、自己不安感、自己不全感が強いためその発表はためらっていたようだ。
ダーウィンはさまざまな事実や事象を、進化あるいは種の変化というキーワードで観察し続け、仮説を立て、仮説に一致しないと仮説を変更して考察し直し、誰からも非難を受けない、あるいは誰の非難もかわすことのできる完璧な理論を打ち立てようとした。結果、曖昧な論考となった。類推は可能であっても、長大な進化の過程を完璧な理論で説明しようとするのは不可能である。そこに完璧主義者ダーウィンの苦悩があったのではないか。またダーウィン自身、進化論(自然選択説)が誤りではないかと自ら疑うこともあったらしい1)。
もう一つは、当時のキリスト教世界にあって、この世の全ては神が創造したと皆が信じているのに、それを覆せば大きな批判を浴びるという恐れがあったのかもしれない。当然、ガリレオの宗教裁判のことは知っていたであろう。 しかし、若い博物学者アルフレッド・ウォレスの追撃のため、重い腰を上げ、『種の起源』を発表しなければならなくなった。同書では動物の変異に関する記述や観察例が延々と綴られた後、最後のほうで、種の変化について誰も気がつかないくらい慎ましく、曖昧に記載されているらしい。
結果、その曖昧さが功を奏し、進化論の先人争いに勝利したダーウィンはその後も自分の仕事を着々と進め、進化論の父といえばダーウィンということになった。もしダーウィンが物事の進め方を少しでも急いだら、あるいはダーウィンの理論がクリアカットであったら、非難の的となりダーウィンの名は残らなかったかもしれない。ダーウィンが生物の進化あるいは変化から学んだことは、「ごく僅かに変化する」あるいは「曖昧に変化する」ことが淘汰されないコツだということではないか。専門用語では「漸進的進化」と言うらしい。
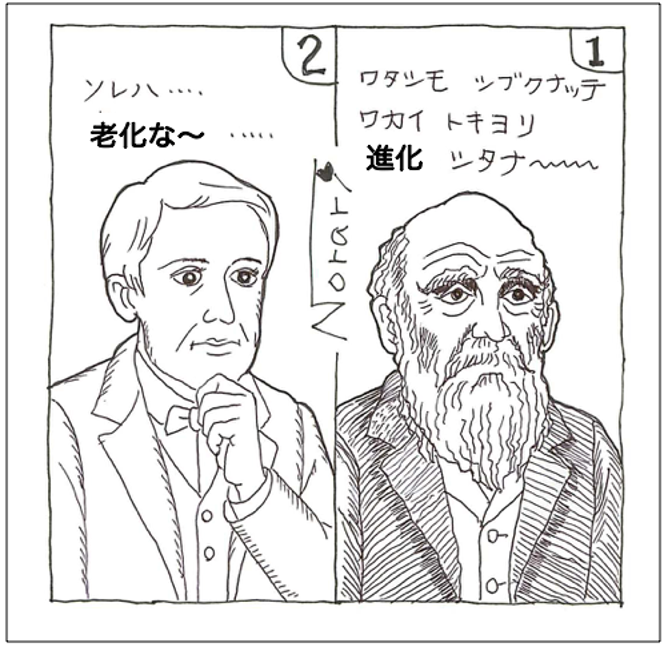
実はダーウィンの成功は、曖昧なところにあったのでは?
文献
1)養老孟司:考えるヒト.p136,筑摩書房,2015.
<付録「宮沢賢治① 脳科学者としての賢治」も続けてどうぞ!>
(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?