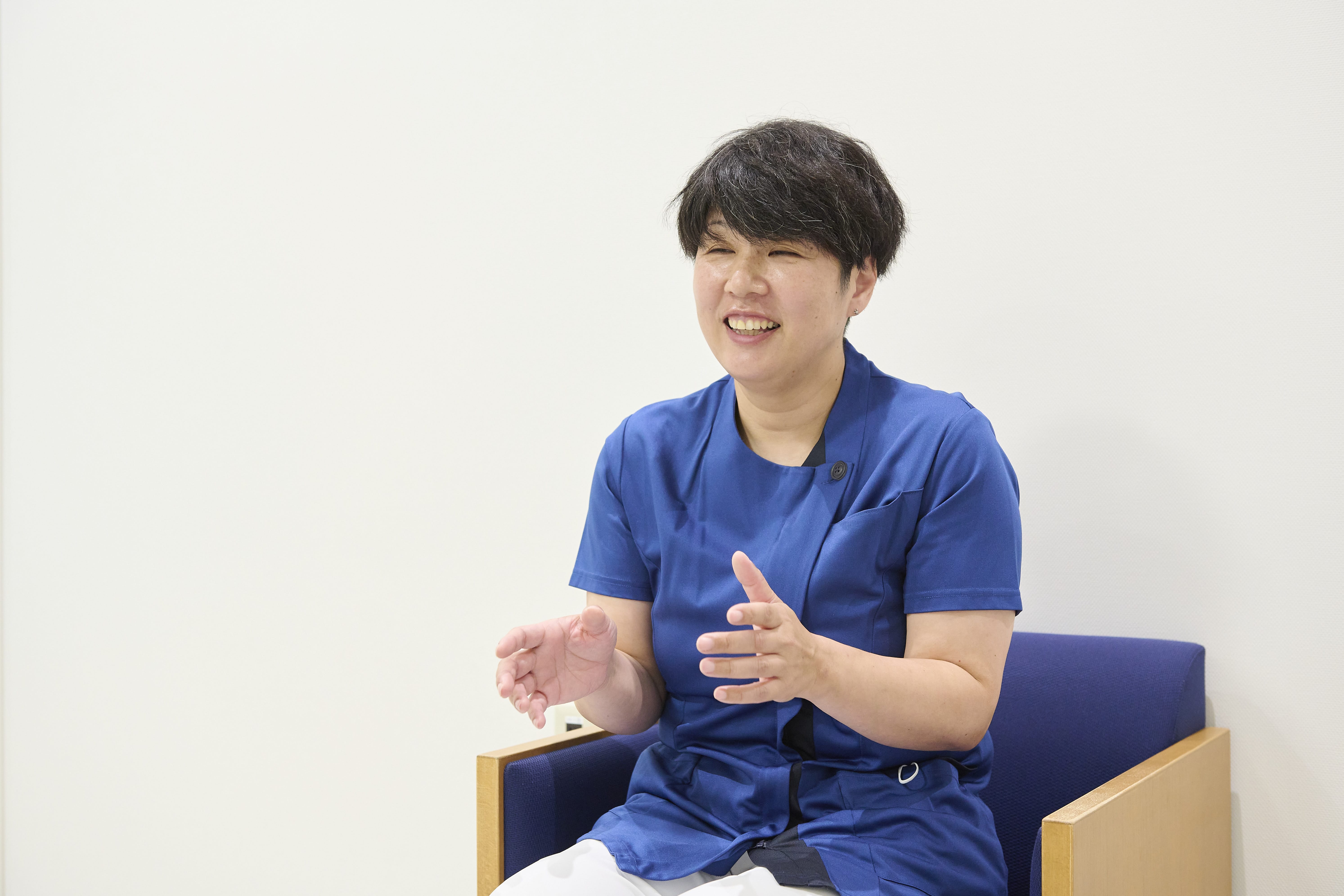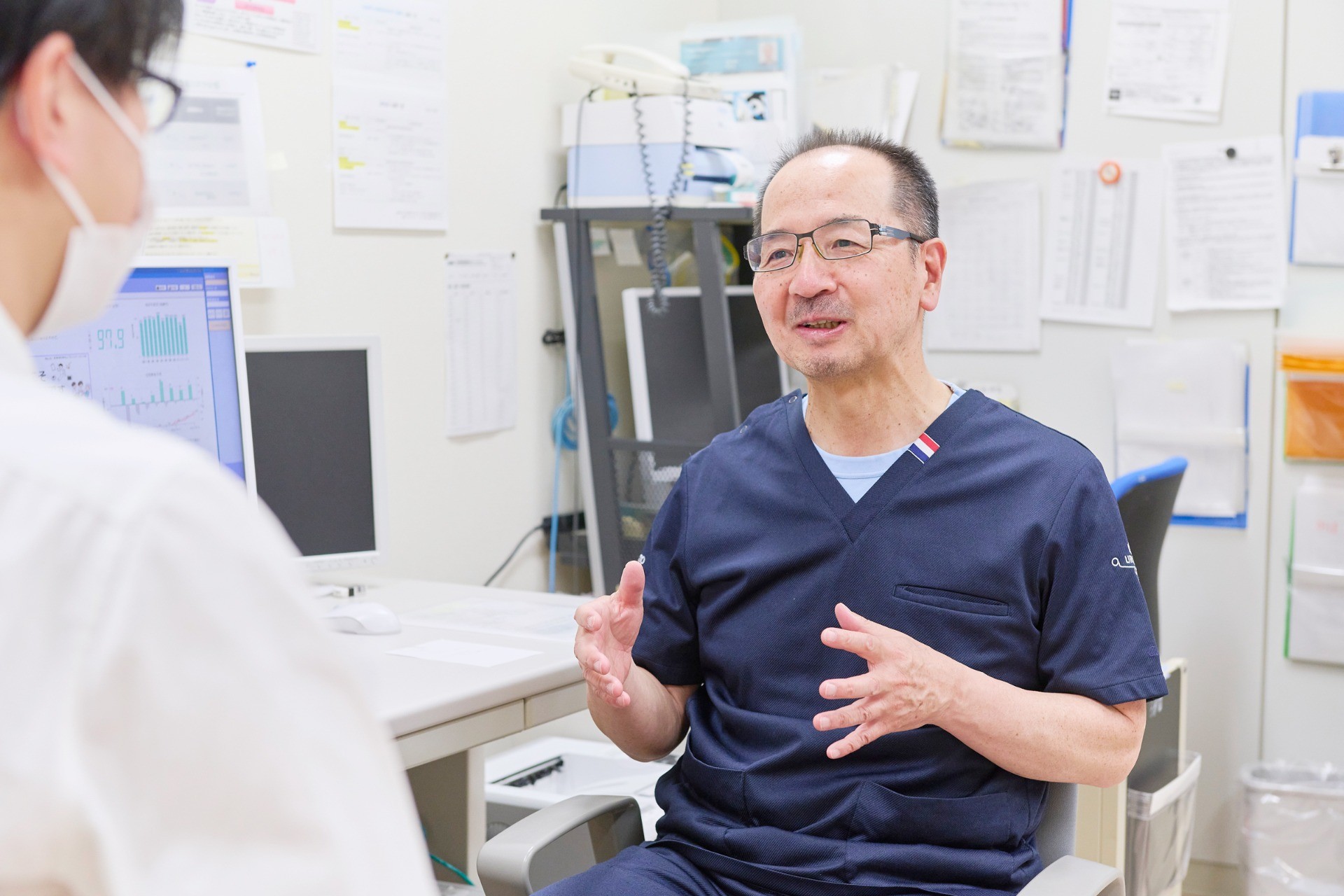地域の救急医療の受け皿となって「断らない救急」を目指す
一本木 邦治 IPPONIGI Kuniharu
救急科では「24時間365日、患者さんを断らない救急」を目指して日夜取り組んでいます。急な病気やケガでお困りの方々をスムーズに受け入れるためにどんな体制を整備し、どんな思いで臨んでいるのか、救急科部長・救急センター長の一本木邦治医師に伺いました。
24時間365日、地域の救急患者を広く受け入れる
救急科では、主に緊急性の高い患者さんや集中治療を要する方の診療に従事しています。救急科専属の医師が常駐し、信州大学からの協力で来る医師1名、研修医2名も含め、平日日中は4~5名体制で患者さんを受け入れています。さらに夜間や休日は各診療科の医師が当直体制を組んで常時待機しています。重症な四肢外傷の患者さんに対しては「四肢外傷・機能再建センター」で形成外科や整形外科を中心に、場合によっては救急科も一緒に診療することも。「24時間365日、断らない救急」を実現するのは大変ですが、忙しい中でどう質の高い診療を提供できるかを考え、全員で共有しながら臨んでいます。
救急科でお会いする患者さんやご家族の多くは、突発的な病気やケガで動揺されています。その時に私たちができるのはお気持ちをしっかり受け止めること。看護師も交えてお話を聞いて治療の方向性などを分かりやすくご説明し、スムーズに受け入れてもらえるよう配慮しています。
脳卒中センターとして脳卒中の急性期治療を積極的に実施
当院で力を入れて取り組んでいる疾患の1つが脳卒中です。「一次脳卒中センター」の認定も受けており、地域の急性期の脳卒中患者を積極的に受け入れ、血栓回収療法などの急性期治療を行っています。当院の脳卒中センターには24時間365日、脳神経の専門医が常駐しているので、「時間との戦い」と呼ばれる脳卒中の治療を速やかにスタートできるのが強みです。
片側の手足が動かしづらい、ろれつがまわらない…。このような症状が出たら脳卒中の疑いがあります。そんな時は迷わず、すぐに救急車を呼んでください。もし救急隊から「長野市民病院に運びます」と言われたら、安心して私たちにお任せいただければと思います。
救急隊との連携を強化する「救急ワークステーション」を設置
当院は2次救急医療機関の指定を受けています。分かりやすく言うと、脳卒中のような脳神経疾患や心筋梗塞などの循環器疾患をはじめ、あらゆる病気で入院治療を要する患者さんを広く受け入れる病院です。重症例など当院での受け入れが困難な場合には、3次救急医療機関である長野赤十字病院や信州大学医学部附属病院などにお願いすることもあります。長野県内では信州大学の医局関連の人があちこちの病院にいますし、私自身は長野赤十字病院にも勤務していたことがあり、地域の先生方との連携はスムーズです。
救急科では消防局の救急隊との協力体制も欠かせません。その要として院内に設置しているのが「救急ワークステーション」です。そこでは救急に関する知識・技術を維持し、連携を深めることを目的に、週2回ほど3~4名の救急隊員が当院で待機し、院内スタッフと一緒に仕事や実習などの活動をしています。ワークステーションで顔が見える関係になることで、より迅速で質の高い救急医療を目指しています。
救急隊とともに定期的に開催する、「救急科合同カンファレンス」も大切です。そこでは当院に搬送された症例を振り返り、その患者さんがどんな診断の下でどんな治療を受け、最終的にどうなったのかを検証します。いわば勉強会のような位置づけで、一つひとつの経験を今後に役立てています。
救急車を安易に呼ぶことも、我慢しすぎることも避けてほしい
119番に通報して救急隊が現地に到着すると、救急隊はまず状況を把握し、「その患者さんにとって最善の治療ができる病院はどこか」という視点で搬送先を選定します。
長野県に限りませんが、最近は全国的に救急車を呼ぶ人が増加傾向にあり、この傾向は今後もしばらく続くと予想されています。重症で救急車を呼ばざるを得ないといった人が多いですが、高齢のために自力で病院に行けないといった理由も多くなってきている印象です。救急車の数は限られますので、症状の軽い方が安易な救急要請をすることは望ましくありません。しかし、突然の重い病気やひどい怪我など緊急性が高いときは、すぐに救急車の要請が必要です。
中には、救急車を呼ぶべき状態でありながら、頑張って徒歩で来院される方もいます。過去の例を紹介すると、事故にあって重症な状態なのに救急車を断り、後で受診してみると実は首の骨が骨折していた、ということもあります。高齢になると症状を感じにくい、救急車で運ばれることに抵抗があるなど事情はさまざまですが、無理して我慢する方も多いようです。最終的には個人の判断になりますが、「これはちょっとまずい」とご本人が思うなら救急車を呼ぶのが基本とお考えください。
万一の災害に備え、機動性のある救急体制を整備
大規模災害や多くの傷病者が出る事故などが起きた時、当院は「地域災害拠点病院」「長野県DMAT(ディーマット)指定病院」として、地域で中心的役割を担わなければなりません。救急医療を必要とする人があふれる状況下で、当院では平常時以上に多くの患者さんを受け入れられるように日頃から体制を整えています。
DMATとは、災害発生時に速やかに出動する災害派遣医療チーム(Disaster Medical Assistance Team)のことで、当院では院内にDMATを組織しています。DMATは1チームにつき医師1名、看護師2名、さらに業務調整員と呼ばれる事務担当者2名の約5名で構成されます。このメンバーは日常業務の傍ら、1年を通してさまざまな専門訓練に参加し、いつ災害が起きても迅速に対応できるよう常に備えています。令和6年能登半島地震では当院から計4チームの派遣をしました。
コロナ禍で得た教訓を今後の救急医療に役立てていきたい
ここ数年で私たちにとって大きな試練だったのが、新型コロナウイルスの流行です。「コロナ禍は災害ではないか」という意見もあったほど、実際に災害さながらの大勢の人が病院に押し寄せました。皆さんもご存じの通り、一口にコロナと言っても症状はさまざまで、特に多いのが発熱です。しかし、発熱がなくても陽性となり得る病気だけに、どうやって感染を予防すればいいのか試行錯誤の毎日でした。受診される方は皆さん陽性の可能性があるため、症状が軽い人は屋外のテントで、症状が重い人は屋内で、診療スペースを分けて診察する流れを作りました。
しかし、具合の悪い方をすぐに診ようと思ってもなかなかルール通りには運びません。感染予防の防護服を着脱することに思いのほか時間を取られ、診察時間が長引いて大変でしたね。不測の事態が起きると平常通りの診療ができなくなってしまう、それがいかにもどかしいかを痛感しました。
コロナ禍の医療は、災害下の医療と少し状況が似ていたかもしれません。でも、どうすれば効率良く診療できるのかを考えて動く中で、若いスタッフも成長したのではないかと思います。この経験を無駄にすることなく、今後に活かしていきたいですね。
個々の希望や個性に合わせた指導で、研修医の成長をサポート
当院では精神科以外の診療科はほぼ常勤の医師がそろっており、各科のことをしっかり学べる環境です。あらゆる疾患の患者さんを診療しながら、大きな学びを得られる病院ではないか。研修医からはそんな意見を耳にします。大学の医局から来る若手の医師もいて、何でも気軽に相談しやすい雰囲気もありますね。
研修医は必ず1度は救急を回るルールがあり、私たちは毎年さまざまなタイプの研修医と出会います。深い興味を持って救急に取り組む人もいれば、他科を希望する中で救急の経験も積もうとする人もいます。救急の仕事は比較的オン・オフを分けやすいためか、救急医を目指す研修医の中には女性も多いようです。私たちは研修医個々の希望やキャラクターを踏まえて仕事を割り振り、指導するようにしています。
私が研修医だった頃の話をしますと、初めて救急科を経験したのは大学病院でした。研修医が担当する仕事が多く、かなりハードな毎日でしたね。でも、大変さと同時に挑戦する価値も大きいだろうと考え、救急科に進むことにしました。ドクターヘリやドクターカーのように、救急科では患者さんが病院に到着する前からできることが多くあります。思った以上に仕事の範囲が幅広いところも、やりがいがあると感じています。

救急車を呼んだ時、どの病院に搬送されるかは地域のバランスによって決まる
皆さん救急車を呼ぶ時はかかりつけの医療機関を指定することが多く、当院でもそのような患者さんが運ばれたら速やかに治療を始めています。しかし、混雑していれば当院で受け入れられないことがあり、あるいは逆に、他院をかかりつけとする患者さんがそちらで受け入れられず、当院に運ばれることもあります。このように、その時のタイミングによるので必ずしも希望が通るとは限りません。現地で救急隊が判断せざるを得ないという事情を知っておいていただければと思います。
万一に備えて皆さんにお願いしたいのが、普段どんな病気でどんな薬を使っているかという情報を分かるようにしておくことです。ご家族が救急車に同乗されることがよくありますが、緊急治療を行う際に薬に関する情報がすぐに分かると助かります。スムーズに治療を開始しやすいので、あらかじめご家族の間で情報共有しておくことをお勧めします。