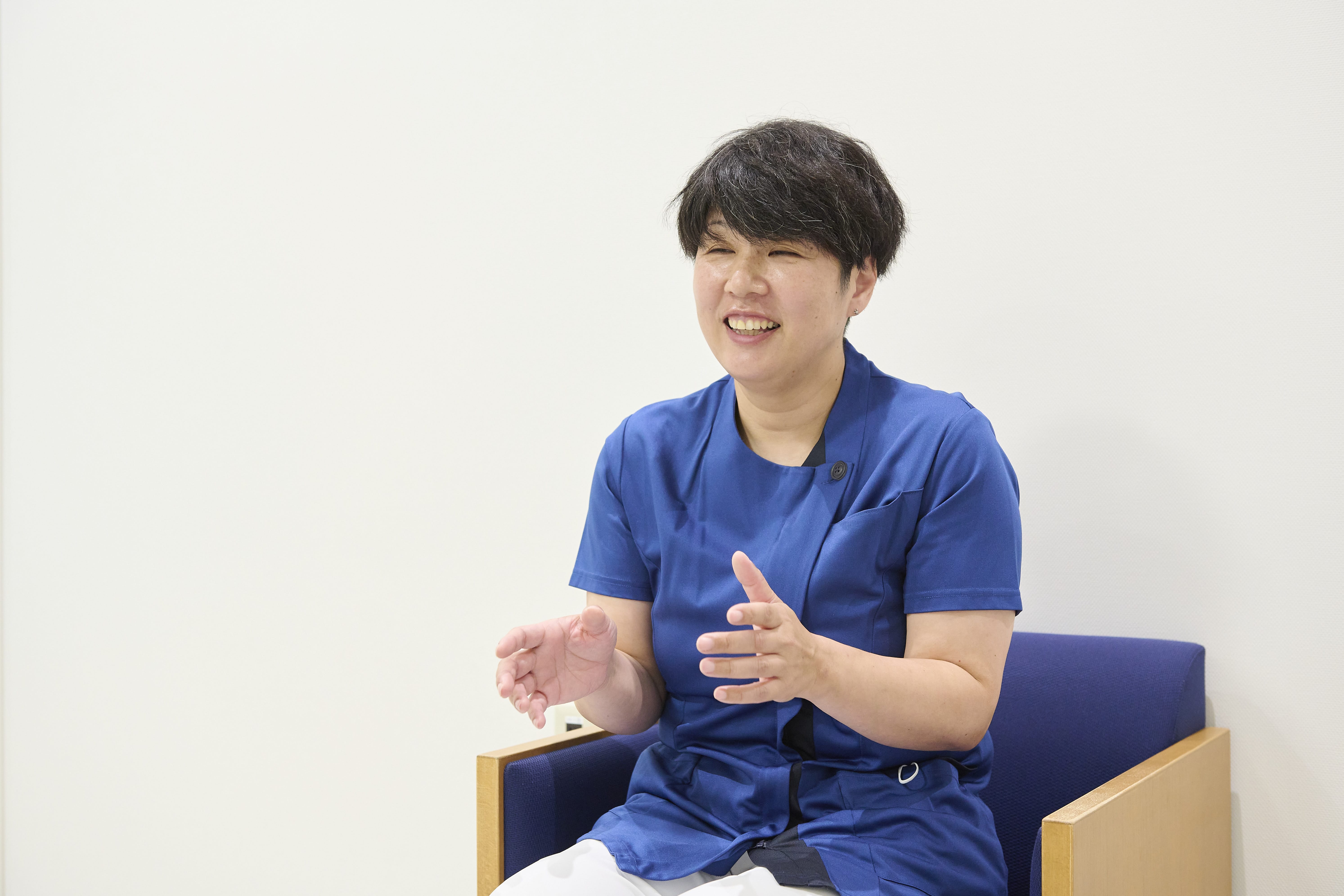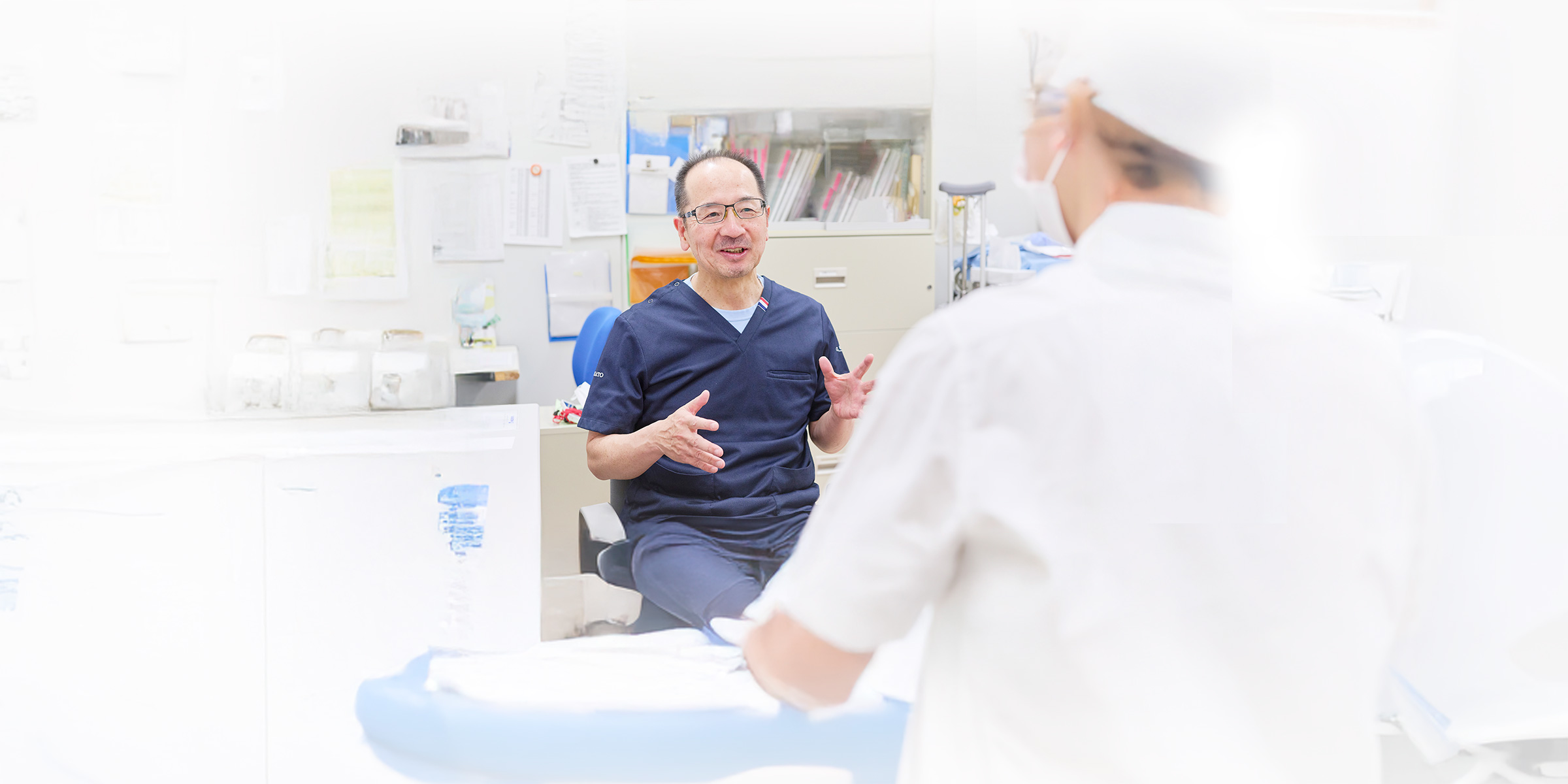
ロボット支援手術により、 体の負担が少なく安全・安心な治療を提供する
加藤 晴朗 KATO Haruaki
合併症を起こすリスクが低く、出血が少なく手術後の回復も早い。手術支援ロボットの導入により、このように患者さんの負担が少ない手術が可能となりました。この手術に携わってきた医師として日々感じることや今後の展望について、 ロボット手術センター長の加藤晴朗医師に語っていただきました。
2022年4月、
ロボット支援手術センターを開設
当院では手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を2013年に導入し、早いもので10年以上経過しました。この手術が日本で始まった当初、保険が適用されたのは前立腺がんの全摘術のみで、しばらくの間は当院でもほぼ泌尿器科が独占しているような状況でした。ところが現在では、この手術は多くの領域に広がっています。前立腺がん、膀胱がん、上部尿路上皮がん、腎がんといった泌尿器科の悪性腫瘍に加えて、胃がんや直腸がん、肺がん、子宮がんなど、泌尿器科以外の診療科でも保険適用となる疾患が増えました。そこで機器の稼働状況をコントロールしながら病院全体で有効活用する目的で、2022年4月、ロボット手術センターを開設する運びとなりました。
センター開設当時はダ・ヴィンチは1台体制でしたので、手術支援ロボットが稼働する週5日のうち、週4日を泌尿器科が、残る1日を消化器外科や呼吸器外科、婦人科が使っていました。どの診療科の医師も手技がますます習熟してきて、今後は泌尿器科以外の手術枠を増やし、2台体制を要望する声が大きくなってきていました。

万全の協力体制と豊富な手術実績が強み
当院のロボット支援手術は週2例のペースでスタートし、まもなく週3例、週4〜5例と件数が増えてきました。当院のほか、長野県内にはこの設備を持つ医療機関が当院を含め8施設(2025年3月現在)ほどありましたが、当センターの強みは何といっても豊富な実績にあります。スタッフの協力や理解がなければ手術枠が増やせないので、院内の協力体制が整っていることもありがたいところです。婦人科では1日2件のロボット支援手術も可能になっています。
2024年6月に新たに待望の「ダ・ヴィンチXi」を追加導入することにより、2台体制の運用を開始し、多くの患者さんに早期にロボット支援下手術が実施できる体制を整備しました。2台体制になって、消化器外科、呼吸器外科、婦人科の手術でも順調に稼働していて、ダ・ヴィンチ手術の恩恵を受けられる患者さんが増えてきました。手術件数についても、ダ・ヴィンチ導入から約11年半となる2024年9月に2,000例に到達しています。
改めて振り返ってみると、私が泌尿器科の医師になった頃はロボットによる手術がここまで広まるとは予想だにしていませんでした。その当時、泌尿器科で1番大きな手術は膀胱全摘と尿路再建を行う膀胱がんの手術で、大学病院で10時間もかかるような手術でした。かなり出血が多く大変なので、よほど熟練したベテラン医師でなければ難しい手術とされた時代です。それがまさか内視鏡で、ロボットを活用した手術を行う日が来るというのは実に感慨深いですね。

従来の手術では不可能だった
繊細な手術が可能に
かつて開腹手術が当たり前だった頃は、手の感覚、触覚のようなものを頼りに、例えば泌尿器科では骨盤の奥深くにある前立腺を摘出したりしていました。一方、ロボット支援手術では奥深い場所まで内視鏡を挿入するので、従来は目で見えなかったところも含めて拡大鏡で細部までしっかり見ることができます。このように、ロボット支援手術は「視覚」に頼るという点が大きな特徴です。「患者さんの体の中に医師自身が入って、目の前まで行って手術をしているような感覚だ」とよく言われるのですが、本当にそのようなイメージです。手術中の操作も非常にすぐれています。自分の手よりはるかに器用に動かすことができるので、骨盤の奥深くのような狭い場所でも正確な手術を行うことが可能です。
ロボット支援手術は触覚に頼れないため、そのことが手術をする上で危険なのではないか、安全性に問題はないかと言われた時期もありました。しかし不思議なもので、モニターを見ながら手術経験を積むうちに、質感や触感のようなものが視覚で分かるようになってきます。私はこれを「触覚が生えてくる」とよんでいます。糸を縛る時の力加減などの力覚は分からなくても、組織が変形する様子が拡大視野で人間の目以上によく見えるので、触感を直感できるようなところがあります。
合併症のリスクが低く術後の回復が早いので、
患者さんの負担が少ない
手術を受ける患者さんにはさまざまな不安があると思います。その1つが合併症です。術後に何らかの障害が残るのではないか、そんなふうに心配される方がおられるのも無理はありません。事実、手術支援ロボット導入以前の開腹手術では一定の割合で合併症を起こすことがあり、「そんな手術は嫌だ」と拒否する患者さんもいらっしゃいました。しかし、私たちが多くのロボット支援手術を実施してきた中で、幸い大きな合併症が起きたことはありません。ロボット支援手術では、開腹手術以上に臓器の解剖がよく分かるので、組織へのダメージを最小限に抑えつつがんを取り除くことができるのです。手術中に万一のトラブルが発生すれば開腹手術に切り替えることもあると事前にお伝えしていますが、現在まではそのようなことも起きていません。
術後の回復スピードも、開腹手術とはまったく違います。泌尿器の病気で言えば、例えば膀胱全摘の開腹手術は患者さんも医師もかなり体力を使う手術でしたが、現在は膀胱を摘除して尿路再建を行っても、翌日から水分摂取が可能で歩くこともできます。準備や手術時間には開腹手術より少し長くかかることもありますが、合併症が少なく出血も少ないから患者さんの体の負担が軽い。これはロボット支援手術だからこそできることです。重症の合併症を起こすことなく、身体機能が早く回復するようになった患者さんの姿を見ると、医師として大きなやりがいを感じます。
手術以外にも幅広い治療の選択肢を提示し、
患者さんと一緒に検討する
ロボット支援手術だけが治療のすべてではないとお話ししましたが、がんに対しては手術以外の治療も広く行っています。放射線治療のほか、抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬、分子標的薬など手術以外の選択肢も増えてきました。ただし、手術同様、どんな治療でも副作用などが出る可能性がゼロではないので、どの治療を選ぶかは患者さん次第です。患者さんごとにリスクなどをトータルに勘案し、ケースバイケースでご相談しながら検討しています。

次世代を担う若手医師の育成にも注力
当センターでは若い医師の育成にも力を入れています。ロボット支援手術には、医師の習得スピードが非常に速いという特性もあります。100例の手術を経験しないとある程度のレベルに到達しないのが腹腔鏡手術だとすれば、ロボット支援手術は10例、20例経験すればスタンダードなレベルに達するようなイメージです。
ロボット支援手術では、手術中の様子がモニターにすべて映し出されるので、若手の医師はそれを目で見て覚えるようなところがあります。私がこの手術を始めた頃に比べると、長く助手をしてきた医師は上達するまでの期間が短く、どんどん成長して次の術者として1人立ちしています。尿が漏れないように私が苦慮して開発してきた方法も、見るだけであっという間に覚えてしまうほどです。指導する側としては嬉しいような、でもちょっと悔しいような。複雑な気持ちですが、医療の進歩のためなんだと自分に言い聞かせています(笑)。
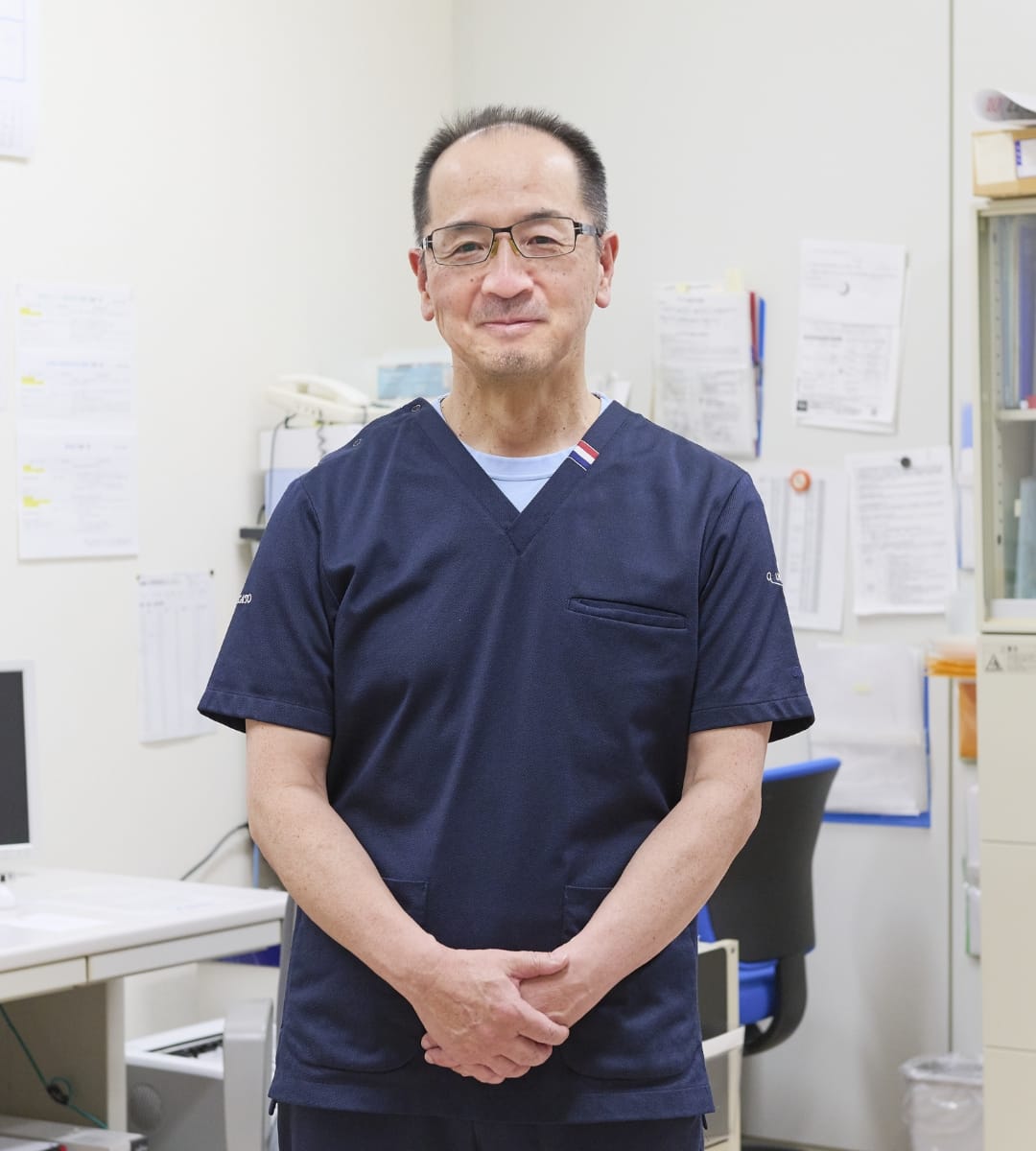
ロボット支援手術のメリットを
地域の方々に知ってほしい
現状の手術支援ロボットは少しごつい感じがしますが、さらに小型化が実現すれば、将来的にはもっと繊細な手術が可能になっていくでしょう。ロボット支援手術は非常に巧緻性が高いので、私個人の直感としては、体腔内の手術がすべてロボット支援手術になる日が来ても不思議ではありません。ロボット支援手術は今後も広く浸透してくる手術であるため、多くのメリットがあることを地域の皆さんに知っていただけるとうれしいですね。当センターには豊富な実績の中で腕を磨いてきた医師がそろっていますので、分からないことがあればお気軽にご相談ください。