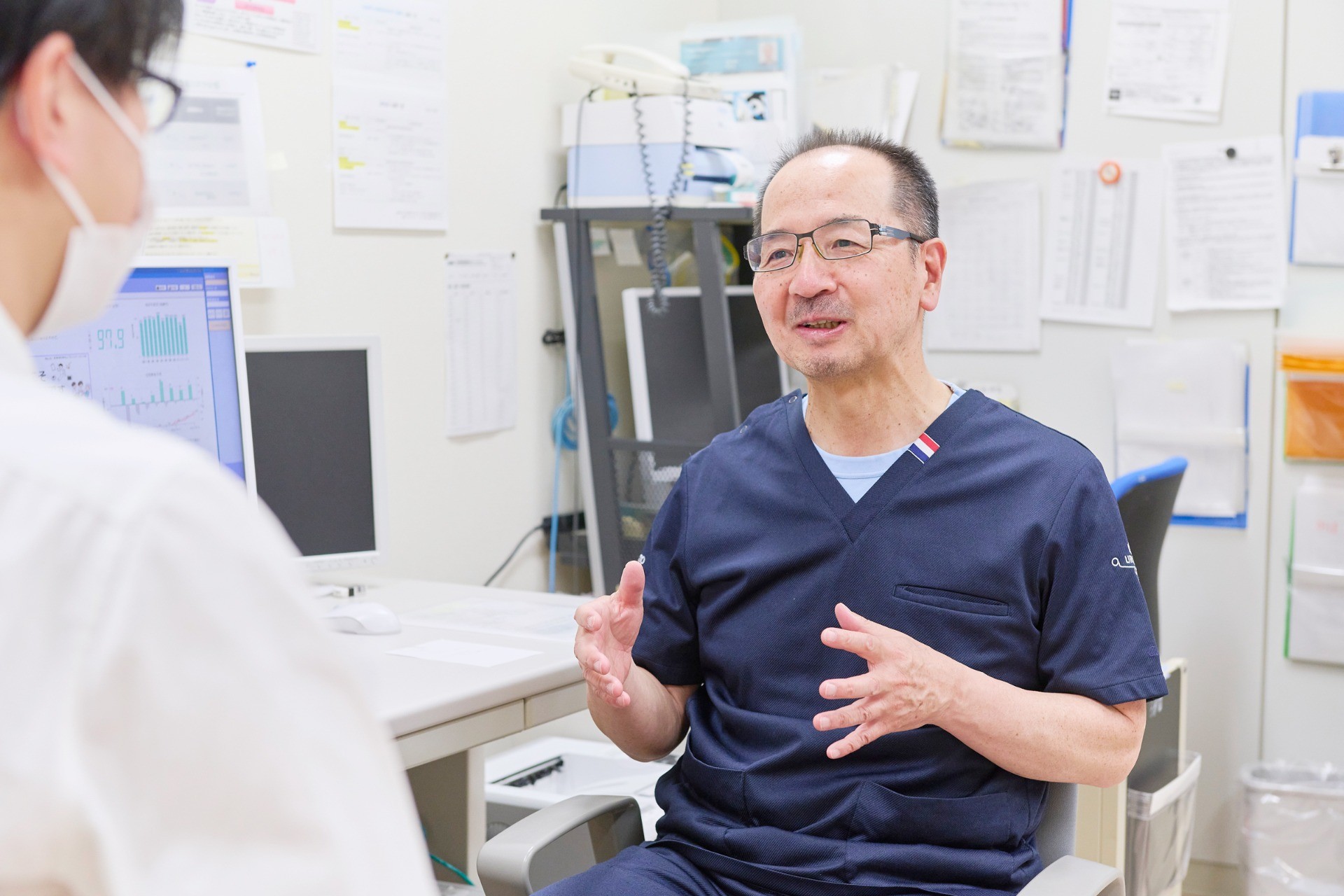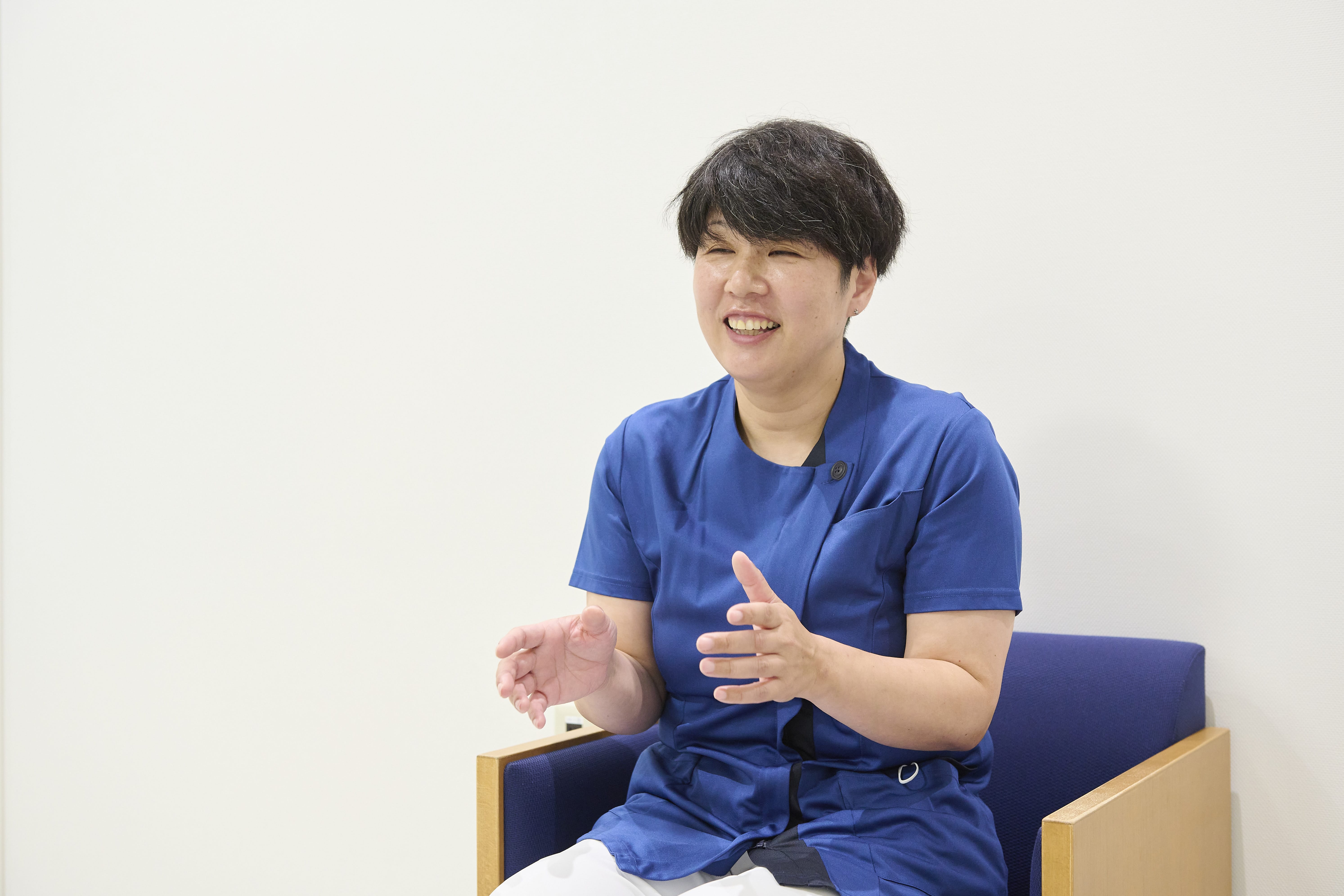
がん看護に携わる看護師が
患者さんために何ができるか
加藤 純子 KATO Junko
長野市民病院は地域がん診療連携拠点病院であり、中核病院としてがんゲノムを含め、全ての治療に対応できるよう、体制を整備しながら実績を重ねている。「がんセンター」は、放射線治療、化学療法、緩和ケア、がん相談支援、がんゲノム医療の5つの機能を集約することで院内横断的な治療体制を強化、がん専門資格を持つメディカルスタッフを配置し、質の高い医療を提供している。乳がん看護認定看護師、認定遺伝カウンセラー、がんゲノム医療コーディネーターの資格を持つ加藤純子看護師に日々の業務や役割、思いについて聞いた。
姉の影響を受け、看護の道に進む
私は学生時代、人とコミュニケーションをとるのが苦手だったので、システムエンジニアを志望し、工業高校に進学しました。けれども看護学校に通う姉から、患者さんとどのような関わりをしているか話を聞いているうちに看護に興味を抱くようになり、進路を変更し看護の道に進みました。
新卒から消化器や泌尿器を担当する一般病棟に配属となり、多くのがん患者指導さんと関わる機会がありました。その後、産休・育休を経て化学療法センターへの配属となりました。がん治療や化学療法を取り巻く看護に関心が高まり、患者さん自身が症状を把握しながら対処したり、予防したりする「症状マネジメント」を深く学びたいと思いました。
患者さんの苦痛を取り除くために専門資格を取得
化学療法を受ける患者さんと関わる中で、多くの乳がん患者さんが、抗がん剤の副作用による更年期のような症状、脱毛や皮膚の変化による外見の変化といった苦痛を抱え訴えていました。患者さんが抱える苦痛に対し、対応できる知識やスキルがないことにジレンマを感じていました。起こりうる副作用や症状について事前にしっかり説明することで治療後の生活がイメージできるのではないか、納得した上で治療を受けることで辛さが軽減できるのではないか、患者さんが治療を選択する意思決定の段階から寄り添うことができないか考えるようになりました。それらを提供するためには、専門知識が不可欠で、「乳がん看護認定看護師」という専門資格があることを知り、2014年に取得しました。

チームで支え、全人的に看ることを学ぶ
乳がん看護認定看護師になってからは、看護の考え方や患者さんとの関わりが少しずつ変わってきました。以前は自分が患者さんとより深くまたはより長く関わること、自分がよりより看護を提供することを重視していました。乳がん患者さんの場合、治療が長期間にわたることが多く、患者さんの数も多いので一人で対応するには限界があります。多職種のスタッフの協力を得ながら、チームで患者さんを支えていくことが患者さんにとっても大切だということがわかり、チーム全体をまとめる調整力を身につけました。また病気や症状だけで患者さんを「看る」のではなく、患者さんの生活や仕事等、患者さんごとに異なる背景や抱えている問題を含めて、全人的に「看る」ことを習慣的に行うようになりました。
緩和ケアチームによる専門のケアの提供
がんセンターにはがん看護専門看護師が1名と緩和ケア認定看護師が1名、がん相談支援センターにはソーシャルワーカーが1名配置されています(2024年12月現在)。
センター内に緩和ケアチームを設置、化学療法をしている患者さんや緩和ケアの入院患者さんたちと頻繁に情報交換を行い、常に情報のブラッシュアップを行っています。2023年に化学療法センター、緩和ケアセンター、がん相談支援センターを集約化した「がんセンター」をオープンし、臨床腫瘍科、緩和ケア内科の診察室もがんセンター内に移動しました。それぞれの機能を集約することで、患者さんの利便性の向上を図るとともに、がん看護に関わる専門的なスキルを他部署と連携して提供しています。
AYA世代への対応にも注力
さらに、病院としては40歳未満のAYA世代のがん治療の対応にも力を入れて取り組んでいます。若い患者さんは数としては多くはありませんが、一定数いらっしゃいます。AYA世代は就学や就労、結婚や妊娠等のライフイベント等、中高年や高齢者とは違う課題を抱えています。最近は婦人科のスタッフが主体となって、がん患者のための生殖医療チームを立ち上げ、妊孕性(にんようせい)温存に対する技術を提供しています。抗がん剤治療を始めると卵巣機能が低下して妊娠する力(妊孕力)が落ちることがありますので、妊娠を希望されている患者さんには妊孕性温存のための相談にも応じています。
外見の変化による苦痛を軽減するアピアランスケアについても定期的に情報発信し、支援できるよう準備を進めているところです。若い世代は学校に通っていたり仕事をしたりしている人が多く、来院する時間も限られるので、動画配信など、SNSを活用して積極的に情報発信を行っていきたいと考えています。

がんゲノムの相談窓口を開設
2019年6月にがん細胞の遺伝子(ゲノム)の変化を調べる一部の「がん遺伝子パネル検査」が保険適用となりました。当院も信州大学医学部附属病院の連携病院として2021年10月から検査を実施しています。この検査を保険適用で受けるには標準的な治療が終了しているなどのいくつかの条件があり、患者さんの同意を得た上で行います。検査を受けるにあたり、納得して検査を受けていただけるよう情報提供などの支援を行っています。また、この検査はがんのもつ特徴(遺伝子の変化)に合った治療を探すための検査ですが、調べる遺伝子の一部に遺伝性腫瘍(遺伝性のがん)に関連した遺伝子が含まれるため、遺伝性腫瘍の診断または可能性がわかることがあります。遺伝性腫瘍に関する所見を認めた場合は、その結果の意味を丁寧に説明し、その情報をどう生かしたらいいかを患者さんやご家族と一緒に考えています。
相談には「がんゲノム医療コーディネーター」も対応しています。がんゲノム医療コーディネーターはがんゲノム医療に関する必要な情報を患者さんとその家族に提供し、患者さんが治療法を選択するにあたって、わかりやすく説明、紹介先との調整を行います。当院では看護師2名(他1名)、薬剤師1名、臨床検査技師1名が資格取得者です(2024年12月現在)。
「認定遺伝カウンセラー」として担う役割
2013年に米国の女優さんが自身が「遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)」であること、予防的な治療を行ったことを告白し、大々的に報道されました。乳がん看護の中では、それ以前から「遺伝性乳がん卵巣がん」に関する情報やケアを提供することを求められていました。しかし、遺伝に対する捉え方はひとそれぞれであり、当院では対応できず他院の遺伝子診療部門に行く必要があり、リスクの高い患者さんに勧めてもなかなか受診につながりませんでした。日々対応する中で、専門的な知識や技術の習得の必要性を感じました。院内でも専門職の必要性を求める声が高まっていたタイミングでもあり、2019年に信州大学大学院の認定遺伝カウンセリングコースに進学し、2021年に資格を取得しました。「認定遺伝カウンセラー®︎」は医療職とは違う独立した専門職です。遺伝性腫瘍に関していうと、もともと生まれつきがんになりやすい体質をお持ちの方にその病気や遺伝学的検査に関する情報提供を行い、その患者さんにとって検査を受けるメリットやデメリットについて一緒に考えています。検査後に遺伝性腫瘍の診断がついた場合は、患者さんやご家族の健康管理や治療等の情報を提供し、必要に応じて他院の遺伝子診療部門を紹介します。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群に診断されたら
乳がんは日本人女性の9人に一人が罹患すると言われているがんですが、その5〜10%が遺伝によるものと考えられています。生まれつき遺伝子に変化がある「遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)」の方は、乳がんや卵巣がんだけでなく、膵臓がんや前立腺がんを発症するリスクが高いと言われています。2020年4月に卵巣がん患者さんや一部の乳がん患者さんに「遺伝性乳がん卵巣がん」の遺伝学的検査が保険適用となりました。検査を受けて「遺伝性乳がん卵巣がん」と診断された場合は、がん治療においては手術の方法や化学療法について患者さんがどうしたいか、今後の健康管理についてどうしていくか一緒に考えるようにしています。
さらに検査を受け、診断がつくということは、ご自身だけではなく、ご家族に体質が受け継がれている可能性があることも理解しておく必要があります。また、今後の健康管理をするにあたって役立つ情報ではありますが、発症しているがんだけでなく発症していない卵巣がんやその他のがんのリスクが高いことが明確になると、患者さんによっては毎日が不安でいられなくなることも考えられます。その辺をイメージしてもらうようお話をしています。
認定遺伝カウンセラーの重要な役割
このように遺伝に関する相談には倫理的な内容を含み、心理的な問題にも関わるため高度なカウンセリング技術が求められます。信州大学は北里大学と並んで、2003年に日本で初めて認定遺伝カウンセラーの養成専門課程を開設しました。現在、全国25の大学院に開設されましたが、資格取得者は全国で428名(2024年12月現在)とまだ少数です。
2023年6月に「ゲノム医療推進法」が成立しました。期待と共にさまざまな情報が飛び交っていますが、ゲノム医療はまだ未解明な部分が多く、実際のところ、診断や所見が出て治療につながる症例はまだまだ少ない状況があります。認定遺伝カウンセラーは、遺伝について相談ができる存在ですので、気になることがあれば気軽にご相談いただければと思います。
今まで得た経験から患者さんのために何ができるかを模索
進行乳がんでステージⅣと診断され抗がん剤が効かず徐々に薬の選択肢が減って動けなくなってきている患者さんを担当していました。小さいお子さんがいて、「絶対に死ねない」と頑張っている患者さんに対して、寄り添って話を聞くことしかできませんでした。寄り添って話を聞くこともとても大切なのですが、もっと何か自分にできることはないかを考え続けています。「自分だったら」をヒントにしながら、目の前の患者さんの置かれている状況や気持ちも考え模索しています。

困っていることを何でも相談してほしい
患者さんの中には、診断結果が怖くて受診するのに二の足を踏んでいたり、治療が始まってからも困っていたりすることを、どこにどのように相談していいのかわからない人も多いと思います。相談したいことを理路整然と説明する必要はなく、「困っています」と意思表示していただければ、私たちがお話を聞きながらできることを考えますので、とにかく手をあげてほしいです。「治療の説明を受けたけどよくわからなかった」「治療費が高くて払えない」「仕事が続けられるのか」「子供の世話をどうしたらいいか」等、治療には関係ないと思われることや、医師に言いづらいことでも、お話しながら整理し、どうすればいいかを一緒に考えます。がん相談支援センターに来ていただいても電話していただいてもいいし、外来の看護師に直接話しかけてもらっても大丈夫です。