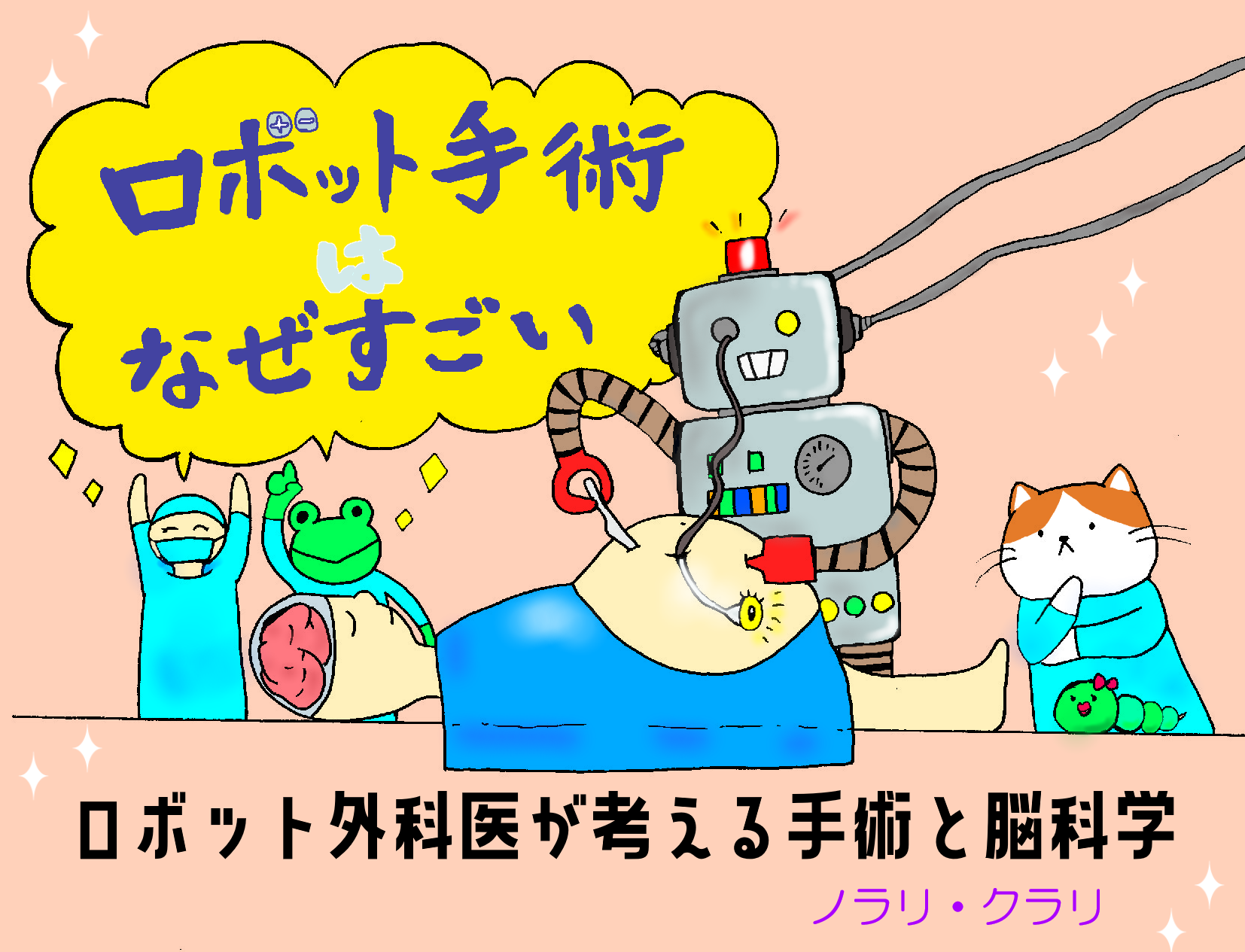お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第33回
2025/06/09
第33回 リスクを冒さないことのリスク
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)
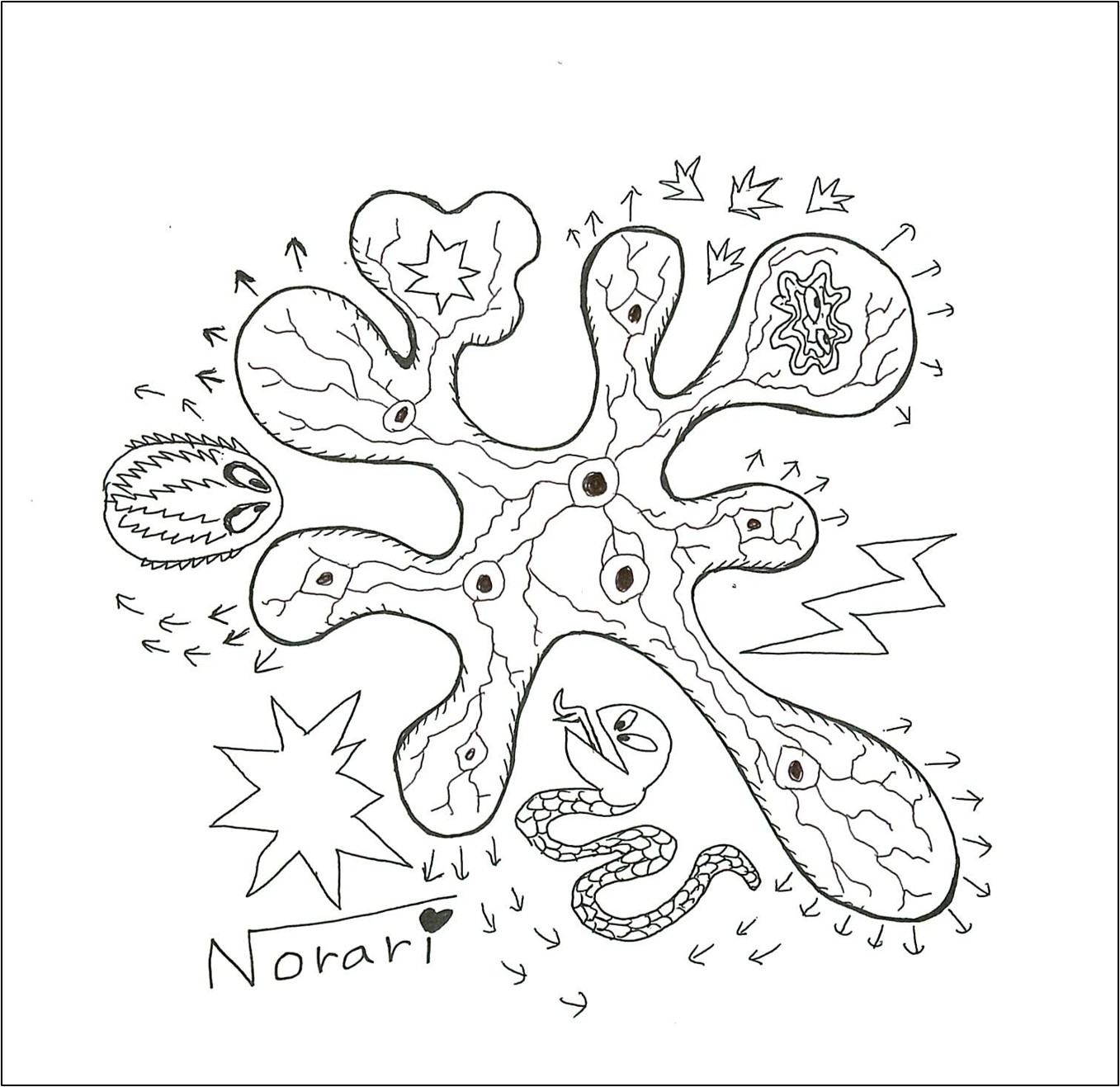
大脳皮質は粘菌のように、時にリスクをかわし、時に飲み込み、時にうまく対処しながら、技能の幅を拡大していく(イメージ図)。
安全か挑戦か
外科医が外科解剖の構造の多くを学び、多くのパターンを身につけるにはどうしたらよいか? あるいは、より難易度の高い手術や危険度の高い手術を安全に行えるようになるためにはどうしたらよいか? 第31回で述べたような手技の安定やマンネリズムに安住するのとは異なり、これらの質問の内容そのままに、つまり多くの構造やパターンを経験し、難易度の高い手術を段階を踏んで、少しずつ挑戦していくというのが正しい答えのように思える。
当然と言えば当然ではあるが、「無謀」と「挑戦」は少し異なる。挑戦するためにはまず自分の今の実力や技術力をよく知る必要があり、そのうえで少し先のレベルに手を伸ばすことによって技量を高めていくのである。一見王道のようだが、多くの外科医はある程度の技量に達したらそのレベルに満足して、それ以上難易度の高い手術には手を出さなくなる。安全を考慮すればそれも正しい選択かもしれないが、自分のそれ以上の成長を阻むことになる。
技量の幅を拡げるには、やはりある程度の挑戦を少しずつ、さらなる未知の構造やパターンにも試みていかなければならない。外科医としての直感を磨くには、ある程度の挑戦を常に試み、多少の失敗も経験する必要がある。失敗したらどうなるか、どう対応するかもパターンの記憶として自分の領域を拡張するのに役立つ。そして徐々に自分ができる手術のレベルが高くなり、さまざまな非定型な解剖構造にも対応できるようになる。
アインシュタインは、「一度も失敗したことがない人は、何も挑戦したことがない人である」と言った。為末大は、「チャレンジしないと、勘の利く範囲は狭まる」「体感しないとイメージは浮かばない」と言う。頭の中でいくらシミュレーションしても、実践は異なるということであろう。真っ当なバッティングコーチは「ボール球には手を出すな」と教えるであろうが、得意なコースであれば多少ストラクゾーンから外れていても、捌き方を練習して打てるようにしてしまう打者もいるのではないか。もしかしたら、強打者ほどストライクゾーンの幅が広いのではないか。
天才ピカソは幼少の頃から、具象画もすでに天才的に上手に描くことが可能であったが、成人してからは、その絵画スタイルを何度も変化させ、破壊と創造――すなわち挑戦を繰り返した。そのなかでもキュビズムはピカソが先導者の一人であり、事物や人物を多視点的に描く、視覚的な実験を絵画の世界で試みたのである。現代美術史のなかでは高く評価されているかもしれないが、個人的には好みではないし、よく分からない。キュビズムのどこが良いのか理解できない人は多いであろう。したがって当時としても、リスクを伴う大きなチャレンジだったはずだ(ピカソ自身はそう思っていなかったとしても)。ただ、一つだけ言えることは、ピカソにキュビズムの時代がなければ、あの名画『ゲルニカ』は生まれなかっただろうし、現代の抽象絵画や多様なスタイルの芸術も生まれなかったかもしれないということだ。
<付録「山下清の場合」も続けてどうぞ!>
(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?