お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第9回
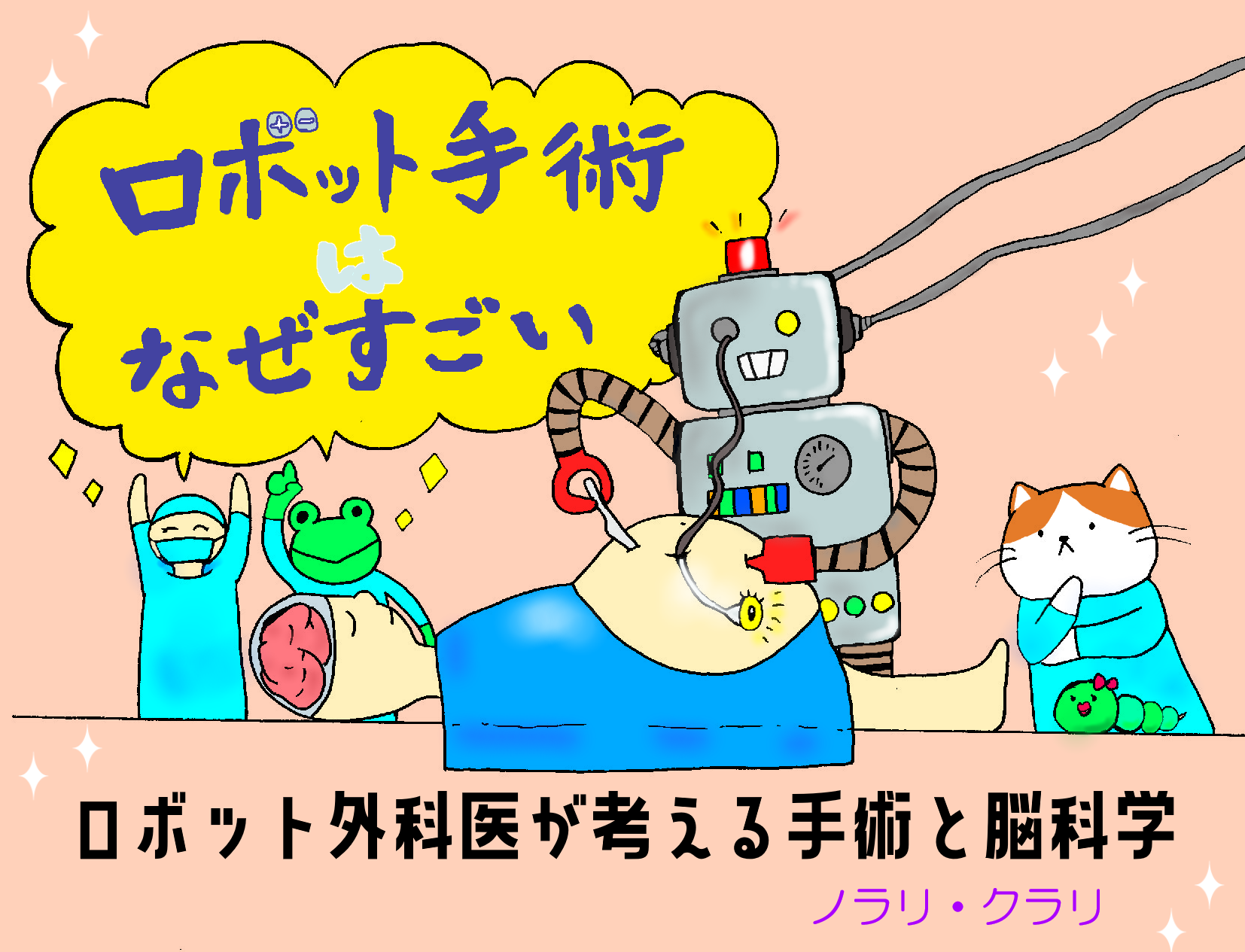
2024/12/23
第9回 鉄は熱いうちに打て
ノラリ・クラリ(ロボット外科医)
手術の臨界期
母国語は、幼小児期に苦労なく覚えるようにみえるが、何らかの理由で成人するまでに普通の母国語環境にないと、それ以降に標準レベルに達するのは困難らしい。臨界期(ある能力や技能を自然に身につけるのに適切な時期:前回参照)には日本語を覚える基本的なニューロン網が残って今後の学習に備えるが、英語の発音や文法に対応できるニューロン網は英語環境にないと間引きされているので、大人になって英会話の勉強に苦労したり、「L」と「R」の発音が区別できなかったりするのは当然かもしれない。また、視覚機能の発達は1歳前後がピークとなり、8歳までしか育たないらしい(視覚の臨界期)。
このように、臨界期なるものがあるように見えるのは、母国語の獲得、ピアノの演奏、絶対音感、多くのスポーツや、将棋、画家の幼小児期の訓練などがある。子どもは将棋の定跡(定石)などは簡単に身につけるので、油断すると大人は痛い目にあう。大人は定跡を理屈や理論で覚えようとするが、子どもはおそらくパターン認識(ニューロン網の形成)で身につけていくのか、意味や理屈にこだわることなく、反射的な反応ができる。
大人が大脳皮質で覚えようとするのとは対照的に、子どもは自転車の運転と同様に基底核で覚えているのではないか? いずれにせよ抵抗なく暗記できる能力は子どもが勝っており、もし臨界期仮説が正しいならば、臨界期とは技能や技術を容易にプログラム化して記憶できる時期とも言える。
われわれ外科医にも、手術の臨界期はあるのか? もちろん技能的な側面が多い外科手術は、若いときから始めるほうが良いに決まっている。しかし、実際には医師国家試験に合格して、ある程度の年齢(25歳以上)になってから開始するしかない。では、なぜ手術の巧拙があるのか? なぜ上手な外科医と下手な外科医が存在するのか? そして上手な手術と下手な手術はどこが違うのか、考えてみたい。
擬似臨界期仮説
一見、成人を過ぎてから開始する手術のトレーニングは、技能を習得するための脳の臨界期をはるかに超えてしまっているように思える。
しかし、手術についてよく考えてみると、1つひとつの技術は「ハサミでモノを切る」「鉛筆で線を引くように電気メスを動かす」「モノを壊さないようにつかむ」、さらに多少特殊なやり方ではあるが「緩まないように糸を結ぶ」など、小さい頃から覚えている技能の応用や、少し練習すれば習得できる技術の積み重ねに過ぎない。仮に臨界期を過ぎてから学ぶことであっても、取り返しのつく技術ばかりである。
われわれは、上手な手術で患者を救うことに憧れて外科医の道を選んだ。手術によってがんや病巣を治すことに生きがいを感じているが、トレーニングの時期はそれ以上に手術の上達や美しい手術ができるようになることをめざしている。優秀な外科医をめざす若い医者たちは、卓越した手術への憧れが内的なモチベーションとなり、トレーニングに打ち込むことができる。
このように強いモチベーションによって、子どものときの臨界期ほどではないかもしれないが、成人を過ぎても臨界期に類似した状況が起こるのではないか。ただし、子どものときの臨界期は無意識であるが、成人後のものはある程度意識的である。脳内には脳由来神経栄養因子(BDNF)という蛋白質が存在し、ニューロンの損傷を防ぐだけでなく、初期段階のニューロンの成長を促したり、脳の細胞間のつながりを強化したりして、学習や記憶力を高めるらしい1)。BDNFはやる気や集中力を促すノルアドレナリンや意欲や活力を促すドーパミンとともに、運動によって量を増やすことができるらしい。したがって、手術がうまくなりたいという強いモチベーションや願望がこれらの脳内ホルモンや因子を産生することによって、擬似臨界期を生み出すのかもしれない。
継続は力なり
何事も初めは難しい、ということわざは、ある意味では真理かもしれないが、より一般的には、何事も初めは容易だ。最後の段階に登ることこそ一番難しく、これに登りうる人間は稀だ、といえる。 ――ゲーテ
それでは臨界期を過ぎて、医師免許を得たわれわれはどのようにして、手術の腕を上達させていくのであろう? 脳科学とは直接関連はないであろうが、「一万時間の法則」といわれるものがある。何事も一流になるには、少なくとも一万時間は必要であると。野球選手になるにも、プロ棋士になるにも、少なくとも毎日3時間練習したり、将棋のことを考え続けたりして、10年間かかる。
ただし、本当にプロで活躍する者は、1日3時間どころではなく、倍以上の時間をかけているのではないか? 四六時中考えているのではないか? 最低が1日3時間×10年間である。ところが多くの者は、毎日3時間は長くは続かない。まず好きであること。ある程度は適性や才能も継続には必要であろうし、飽きないで続けるためには環境や練習の工夫をするなど、さまざまな要因が必要となる。いずれにせよ、今、振り返って手術の上達について考えてみると、「一万時間の法則」に妥当性はあるように思える。「継続は力なり」である。もちろん、実際に執刀している時間だけでなく、手術の予習やシミュレーションをしたり、名人や上級者のみならず、 他人の手術を見学したり、動画を繰り返し見て、復習するなども含まれるかもしれない。
しかし、ほとんどの外科医にとって、毎日実践的な手術に関わる時間を3時間以上確保できる者はごく一握りではないか。たくさんの手術患者さんが集まる病院(いわゆるハイボリュームセンター)に勤務でき、毎日手術をしている“ハイボリュームサージャン”と呼ばれる外科医以外は到底無理な話である。
最近の内視鏡手術は優れたシミュレーターなどを利用して、ゲーム感覚で手技的なことはかなり学べるようになっているが、やはり実際の生体の外科解剖で感じる質感やそれらの取り扱いは実感できない。また唯一、外科手術がほかの技能や技術系の仕事とまったく異なるのは、実物を用いて練習を積めないことである。例えば、料理人であれば、材料費や燃料費さえ惜しまなければ、納得のいく料理を完成するまで練習することができる。また、練習と本番の区別はつけ難いが、時間と場所の確保さえ惜しまなければ、絵画にしても楽器の演奏にしても、筆やカンバス、あるいは楽器を用いてとことん練習することができる。
それでは、実践以外に練習ができないという特殊な職業である外科医はどのようなトレーニングが良いのだろうか? それでも、最終的には実践を繰り返していくことによって手術を上達させていくことになる。いわゆるオン・ザ・ジョブ・トレーニングである。
文献
1)アンデシュ・ハンセン(著),御舩由美子(訳):運動脳.サンマーク出版,2022.
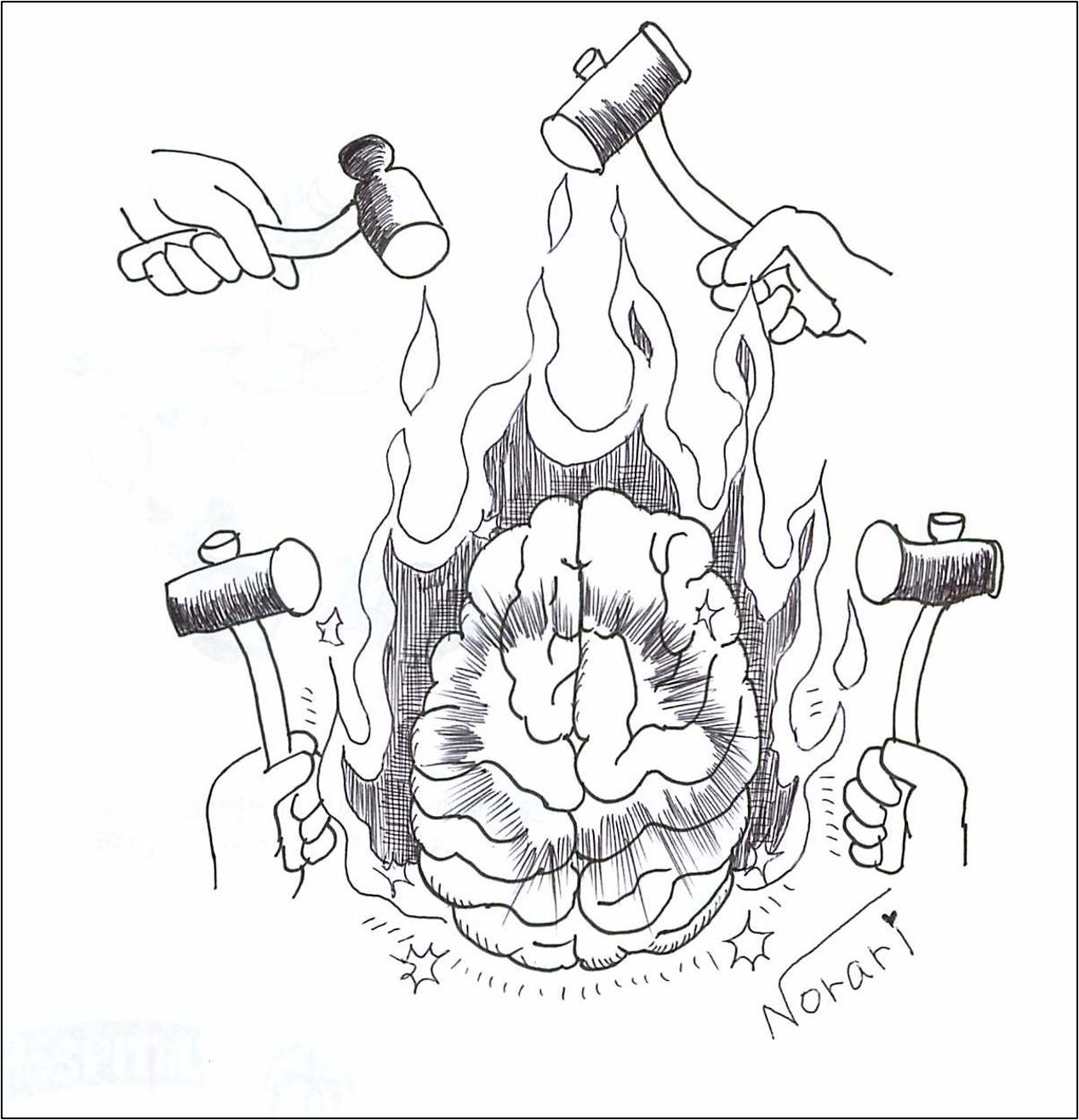
大脳も熱いうちに打てば、何かのプロや達人になりうる可塑性があるのでは
(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)
なにをお探しですか?

